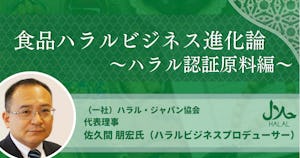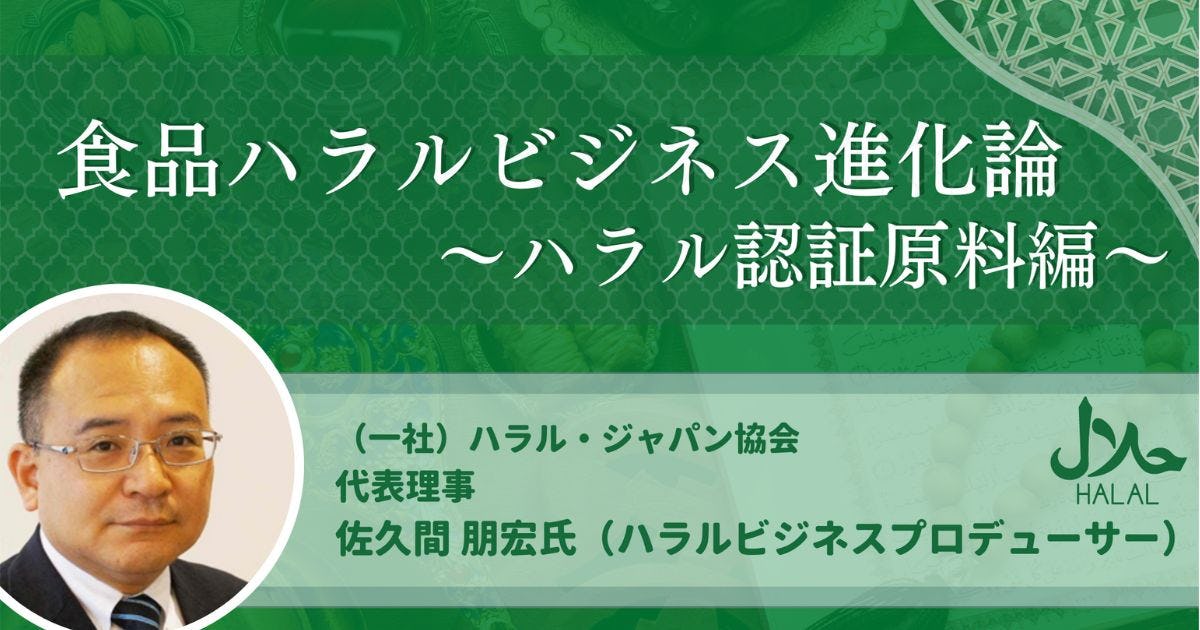
ハラルビジネス進化論まとめ【食品ハラルビジネス進化論〜ハラル認証原料編vol.12】
前回の記事を読む:輸出対応とハラル(ハラール)認証の有効性【食品ハラルビジネス進化論〜ハラル認証原料編vol.11】
こんにちは、ハラル・ジャパン協会の佐久間です。テレビで連日WBC(ワールド・ベースボール・クラッシック)が取り上げられ、盛り上がっています。サッカーだけでなく、野球もまだまだ盛り上がるんですね?小さなころは野球ばかりしていた野球小僧の私にはとてもうれしいです。できたら優勝してほしいです。この記事を書いた時にはイタリアに勝ったところまでです。
今回は「ハラルビジネス進化論のまとめ」ということで解説していきます。ガンバレ!日本!!野球の神様WBCで優勝を!!
ハラルビジネスには経営判断が重要、全社が参入するものではない⁈
12回を通じて話したいことは、原材料を海外に輸出する場合にハラル認証を要求されることが非常に増えてきた今、日本の事業者は真剣にハラルビジネスの基本を学び経営判断できる力をつけることが大事です。参入のタイミングは各社で違います、今すぐの事業者と10年後の事業者がいるかもしれません。そしてハラルビジネスを学ぶときは、常に情報をアップデートすることを忘れないでください。なぜならば、10年前と5年前、そして今年と5年後、10年後は違うと考えられるからです。
ハラルの認証制度を含め、変化し続けています。またエリア・国や商品・カテゴリーによってもハラルビジネスの対応方法が違います。あたふたせずに判断できる体制づくりがとても重要になるのです。これから始める事業者には「ハラルビジネス基礎研修」、すでに取り組んでいる事業者には「ハラルビジネスプロ研修」をお勧めします。そして商品や工場内を一度見せていただければ、ハラル認証が取得できるかどうかの判断ができる「ハラル認証可能性診断」が効果的です。
社員研修とハラル認証可能性診断を行っておけば、経営判断できる材料はある程度できていると考えます。イスラム教の国ではない日本では、ハラルビジネスは同業の5%程度が参入すればいいと考えています。ニッチトップ、下剋上をしたい事業者にはハラルビジネスは向きますが、決して全社が参入するビジネスではないのです。

ハラル・ジャパン協会主催のセミナーの様子
原材料でアジアを攻めるなら、ハラル認証取得が必要な時代に
アジアで売りたいならハラルビジネスへの参入が有効です。政治リスクが少ない国や未来志向で販売、製造できそうな国ならハラルビジネスの可能性が広がります。日本はアジアに属しています。このポジション(立ち位置)を生かせる戦略が、ハラルビジネスには隠れているのです。
輸出は原材料がおすすめですが、付加価値商品(一部の農産物加工品や健康食品など)は完成品輸出に向いています。ということはイスラム市場で、受け皿の工場、日本の工場が増えることも予想できます。やはりハラルビジネスの真骨頂は、現地生産、現地販売だけでなく、プラスαで他国輸出もすることです。進出国選びも大事ですが、ハラル認証でいうマレーシア式(JAKIM)ハラル認証制度で行くか?インドネシア式(BPJPH)ハラル認証制度で行くか?が、現在は大きなポイントです。
輸出・進出+ハラル認証をプロのコンサルタントに頼む時代が来ました。「進出国選定」から始まり、「ハラル認証団体選定」「ハラルビジネスOEM工場選定」などが必要になります。このような環境では最短距離でアジア圏で展開するためには現実的な選択肢に入ってくるでしょう。最後に、アジアを俯瞰してみることが重要で、東アジア、東南アジア、南西アジア、中央アジア、中東・アラブを真剣に考えてみてください。サッカーのアジア予選のエリアのほぼ同じです。ここから始まるハラルビジネスのサクセスストーリーを一緒に歩みたいと考えます。

マレーシアJAKIM、インドネシアLPPOM-MUI(BPJPH移行前の認証)を両方つけたキットカット
皆様1年間12回の連載はいかがでしたでしょうか?原材料のハラルビジネスの可能性を感じていただけましたか?ハラルビジネスを活用してぜひ皆様の原材料が世界に羽ばたく、または日本国内で新しい使われ方をする一助になればと思います。また機会があればセミナーや展示商談会、またはこうして執筆した文章等でお会いできると思います。1年間ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。
(佐久間朋宏/非営利一般社団法人ハラル・ジャパン協会代表理事)
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。