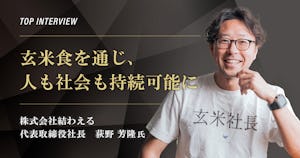着色料とは〜食欲増進や品質保持に貢献!プロの現場で選ばれる食用色素と基礎知識
食品において着色料は、見た目を美しくするだけでなく、食欲を刺激し、製品の品質を向上させる重要な役割を果たします。
この記事では、着色料の役割とメリット、代表的な着色料の特徴、海外展開(輸出)を考える際に注意すべきことのほか、食品表示やアレルゲンによる健康リスクについて解説します。あわせて、シェアシマ掲載の着色料もご紹介。本記事を参考に、開発テーマや条件にあった原料をぜひ見つけてください。
「着色料」をシェアシマで検索する >

食品に使われる着色料(食用色素)とは

「着色料」は、食品が加工や劣化によって変色・退色してしまうのを防ぎ、食品に色付けするために使用される食品添加物のことです。「食用色素」とも呼ばれることもあります。
赤飯や紅白餅、繭玉(まゆだま)など、日本では古くから伝統食や行事食にさまざまな「色」が用いられてきました。着色料は身近な料理にも多く使われてきた歴史があり、食べ物のおいしさを引き立てる役割を担ってきました。
着色料の役割とメリット

現代の食品開発において、着色料は食品の魅力を高めて品質を保つ上で、重要な役割を果たしています。適切な着色料を使用することで、製品の視覚的なアピールだけでなく、品質やブランド差別化にも寄与することができます。
近年では、SNSの影響により見た目(映え)を重視する消費者が増えていることもあり、味や香りに加えて外観の完成度をブラッシュアップすることで売り上げを伸ばしている商品もあります。これらを踏まえ、本記事では着色料の主な役割とそのメリットについて説明します。
視覚的な魅力の向上
食品の色合いは、消費者の購買意欲に大きく影響します。たとえば、鮮やかな色には、食品を新鮮で美味しそうに見せる効果があり、消費者の食欲を増進させます。食品の特徴やターゲットに合わせた色を使用することで、消費者の関心を引き、食品をより魅力的に見せることができます。
品質の保持
食品は保存中に酸化や退色が進むことがあり、見た目が悪くなると品質の低下を感じさせてしまいます。着色料を使用することで、色合いを一定に保ち、製品の品質が保持されます。
また、着色料は製品の安定性を向上させるため、長期保存が求められる商品においても重要な役割を果たします。色が一定であれば、消費者に対して製品の鮮度が保たれている印象を与え、信頼感を高めることができます。
製品の差別化
着色料を活用することで、他の製品との差別化が可能となります。色別のシリーズ展開や季節限定の色を使用することで、消費者に新しい印象を与え、注目を集めることができます。
たとえば、特定のイベントやシーズンに合わせた限定カラーを導入することで、消費者の関心を引きつけ、購買を促進することができます。
さらに、特定の色をブランドの象徴として使用することで、消費者に強い印象を与え、ブランド認知を高めることもできます。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。
着色料の使用が禁止されている食品
食品における「色」は、鮮度や安全性を判断する際に重要な指標となります。そのため、鮮魚や食肉、野菜などの生鮮食品には着色料の使用が禁じられています。これらの食品に着色料を使用すると、消費者が品質や鮮度について誤った判断をする可能性があり、添加物の本来の目的に反するためです。
※参考:東京都保健医療局「用途別 主な食品添加物」
代表的な着色料の特徴と着色料が使われている食品

着色料は、主に「天然着色料」と「合成着色料」の2種類に大別できます。ここでは、代表的な着色料の特徴と利用されている食品例を紹介します。
天然着色料
天然着色料は、植物や動物などの自然由来の素材を原料としています。自然な色合いが特徴で、古くから利用されてきました。しかし、熱や光に弱いため、安定的な供給が難しく、合成着色料よりも価格が高くなる傾向があります。
| 種類 | 特徴と食品例 |
|---|---|
| ウコン色素 |
ショウガ科ウコンの根茎よりエタノール、油脂又は有機溶媒で抽出して得られる。主成分はクルクミンという鮮やかな黄色の色素である。
食品例:食肉加工品、農水産物加工品、栗の砂糖漬け |
| クチナシ色素(赤、青、黄) |
アカネ科クチナシの果実を原料に、抽出や分離、加水分解などで作られる着色料。ひとつの原料から複数の色が得られる。
食品例:菓子、アイスクリーム、中華麺、漬け物 |
| ベニコウジ色素 |
カビの一種「ベニコウジ菌」の培養物を乾燥・粉砕した後、アルコールや有機溶媒で抽出して得られる。抽出に酸性アルコールを用いると黄色の色素になる。
食品例:魚肉ねり製品、味付たこ、畜産加工品、調味料 |
| カラメル色素 |
原料は砂糖やぶとう糖、でんぷんなどが原料で、日本で多く利用されている。熱や光に強く、風味づけの作用もある。
食品例:菓子、醤油、ソース、ビール、清涼飲料水 |
| ベニバナ色素 |
ベニバナの花から抽出されるフラボノイド系サフロミンが主成分。赤みが少なく鮮明かつ透明感がある黄色を呈する。pHの変化にも比較的安定である。
食品例:麺類、菓子類、冷菓など |
| コチニール色素 |
コチニールカイガラムシ(エンジムシ)と呼ばれる昆虫から抽出される赤色の天然色素。pHの変化や光に対しても安定であり、中性域でもきれいな赤色を保つことができる。
食品例:ハム、ソーセージ、飲料、冷菓など |
| スピルリナ青系色素 |
鮮明な青色を呈する天然着色料。熱に弱い。
食品例:冷菓、チョコミント、フィコシアニンの美容素材として(機能性表示食品) |
| 一般飲食物添加物 バタフライピー |
バタフライピーはアントシアニン系の色素を持ち、中性域では鮮やかな青色を呈し、酸性になると赤色を呈する。
食品例:ドリンクなど、酸味のあるレモンなどと一緒に提供され、青色から赤色に変化する様子が「映える」と人気に |
| 一般飲食物添加物 各種(濃縮)果汁 | 濃縮の赤ぶどう果汁やいちご果汁などの色の濃い果汁を使用して着色する。 |
※「一般飲食物添加物」とは、一般に食品として飲食に供される物であって添加物として使用されるものです。
このほかにも、野菜本来の色を活かした着色の方法として、野菜ペーストなどを活用するのも良いでしょう。
合成着色料
合成着色料の代表として「タール系色素」があります。石油を原料としていて、鮮やかな色合いと退色しにくいという特性があります。化学的に合成されているため、不純物が少なく、安定した供給が可能です。
| 種類 | 特徴と食品例 |
|---|---|
| タール系色素 |
原料は石油製品で、化学的に合成された着色料。着色性と色の保持性が高く、少量で効果を発揮する。
食品例:菓子、アイスクリーム、明太子、漬け物 |
| β―カロテン |
合成のβ―カロテンを主成分とした、黄色~赤みのあるオレンジ色の色素。色素としてのカロテンは由来(合成、植物由来、藻類由来)で分けられていて、その中の一種。
食品例:マーガリンなどの油脂、菓子、パン類、清涼飲料水 |
| 水溶性アナトー |
水に溶けないアナトー色素をアルカリ下で加水分解を行って水溶化したもの。耐菌性の高い食用色素としても用いられている。
食品例:チーズ、ソーセージ、タコなどの水産加工品 |
| 銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウム |
植物から得られるクロロフィル中のマグネシウムを堂に置き換えたもの。このうち水溶性を高めたものが銅クロロフィリンナトリウムである。
食品例:野菜類や果実類の貯蔵品、チューインガム、生菓子、チョコレートなど |
※参考:東京都保健医療局「用途別 主な食品添加物」
※参考:食品化学新聞社「食品添加物・機能性素材市場レポート2024」
虫から得られる赤い着色料「コチニール色素」
天然着色料の中には「コチニール色素(カルミン酸色素)」という虫由来のものがあります。これは、コチニールカイガラムシ(エンジムシ)と呼ばれる昆虫から抽出される赤色の天然色素です。
使用例として、以下のようなものがあります。
- 食品:ハム、かまぼこ、菓子、ジュース、キャンディーなど
- 化粧品:口紅、アイシャドー、チークなど
- 医薬品:一部の医薬品の着色
- 衣服:古くは、染料としても
コチニール色素は食品の着色料としては非常に優秀です。科学的に安定していて日光などの光による退色もしにくいという利点があります。ただ、由来が昆虫であること、後述するアレルギーの問題が示唆されていることにより、一部で使用が避けられているのが現状です。日本で販売されているコチニール色素は低アレルギー品が多く流通しています。
着色料の食品表示
食品に着色料を使用した場合は、「物質名」で表示するのが原則です。簡略名や類別名で表示することも可能です。ただし、「着色料(赤3)」のように用途名と併記で表示する、あるいは「赤3」のように色の文字が入り着色料であるとことが明確にわかる物質の場合は単独で表示することが認められています。
商品の容器包装に「着色料無添加」、「保存料不使用」といった添加物の無添加・不使用表示をする場合は、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に沿って消費者に誤認等を与えないように表示をしなければなりません。
※参考:消費者庁「食品添加物表示に関する情報」
海外展開を考える際の注意点
食品添加物は、国や地域ごとにその定義や使用基準が異なるため、着色料の使用が商品の輸出における障害となることがあります。
たとえば、クチナシ色素の場合、赤、青、黄の色素ごとに各国の規制が異なるため、注意が必要です。
| 米国、EU、シンガポール、豪州 | 中国 | 韓国、台湾、香港 | タイ、ベトナム | |
|---|---|---|---|---|
| クチナシ赤色素 | × | × | ○ | × |
| クチナシ青色素 | × | ○ | ○ | × |
| クチナシ黄色素 | × | ○ | ○ | ○ |
一般財団法人食品産業センターでは、主な輸出先10の国・地域 (米国、EU(英国含む)、中国、タイ、香港、豪州、台湾、韓国、シンガポール、ベトナム)に対応した着色料の代替使用に関する規制をまとめた早見表(※)を公開しています。海外展開を視野に入れた商品開発を進める際に、お役立てください。
※参考:JFIA「海外食品添加物規制早見表」(2024年11月時点)
着色料は体に悪い?アレルゲンや健康リスク
「着色料は危険」というイメージを持つ方もいますが、食品の安全性は「何をどれだけ摂取するか」が重要です。科学的に「ゼロリスク」はありえず、どんな食品でも過剰摂取は健康リスクになり得ます。例えば、食塩や糖分の摂りすぎは生活習慣病の原因になります。自然由来の食品にも、アレルギーや微生物による注意が必要なものが多く存在します。
着色料は食品添加物の中でもごく少量で効果を発揮し、特に合成着色料はその傾向が顕著です。使用基準は健康に影響を与える量よりもはるかに低く設定されており、一般的な食生活であれば健康への影響はほぼありません。
一方で、注意すべき例もあります。2012年には、天然着色料のコチニール色素でアナフィラキシーを含む急性アレルギー症例が報告されました。これは、コチニール色素に含まれるカイガラムシ由来のタンパク質が原因と考えられています。現在、日本で流通するコチニール色素製剤はアレルゲンを低減するよう精製されていますが、アレルギー体質の方は原材料表示を確認し、不安な場合は摂取を控えるなどの対策が推奨されます。症例は少ないためアレルギー表示義務はありませんが、個人の体質によっては注意が必要です。
※参考:国立医薬品食品衛生研究所「コチニール色素・カルミン摂取による食物アレルギー」
着色料のご紹介
クチナシ果実に含まれ、生薬成分でもある「ゲニポシド」からつくられる水溶性の赤色着色料です。 熱に対して安定、光に対してはやや不安定ですが、同じく赤色のベニコウジ色素に比べて安定して発色します。 ゼリー、焼き菓子、和菓子、煎餅、飲料・リキュールなどに使用できます。
耐熱性のあるオレンジ系色素です。米菓、スナックシーズニング、中華系調味料、飲料等オレンジ色素が求められる加工食品に使用できます。
色調の幅、用途幅も広いトマト色素シリーズです。トマトリコピンを独自の分散技術によって製剤化し、オレンジ系~赤色~ピンクまで幅広い色調の色素を展開しています。また、通常のトマトリコピンは油脂の多い食品中では黄色く変色してしまいますが、タイショーテクノスでは、耐油性のある「TSレッド・TMZ」も用意しています。
水溶性液体品のカカオ色素製剤です。カカオ豆より抽出して得られる褐色色素で、主成分はフラボノイド類より生成したポリフェノール類です。深みのある茶色に着色できます。
ナス科トウガラシの果実から抽出したトウガラシ色素(主成分:カプサンチン)を水に分散するようにアラビアガムで乳化した着色料製剤です。耐塩性、耐酸性に優れており、着色安定性の高さからレトルト商品、ゼリー、タレ、調味液などの製品におすすめです。
おせち料理やサラダ、ムースなど料理、日本酒などの飲料、ケーキ、チョコレートなどのお菓子、ジャンルを問わず幅広く使える、トラディショナルな金粉切り廻しです。ひとひらで効果的に食材のグレードを高めてくれる、不動の人気を誇るアイテムです。
従来の金箔の扱いにくさを改善し、箔の飛散を防ぎながらもさらさらとした感触を叶えました。特殊加工により、輝きと光沢感もさらにアップ。スイーツ、料理、ドリンクなど簡単にまばゆい輝きをプラスします。ふりかけタイプで扱いやすいのも特徴です。
ヘマトコッカス藻由来の国産天然アスタキサンチン原料です。アスタキサンチンとは、カロテノイドの一種で、エビやカニなどの甲殻類や、鮭、イクラ、鯛など、主に海の生物に多く含まれる赤橙色の色素です。ビタミンEの100~1000倍とも言われる強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素除去能、免疫賦活化、発ガン抑制作用など、有用な特性を持つことが明らかになってきている注目の素材です。
「着色料」をシェアシマでチェックする
着色料を上手に活用することは、食品の見た目や品質を保持・向上させたり、製品の差別化をはかったりするのに非常に有効です。
食品の企画開発をサポートする「シェアシマ」では、無料の会員登録で、商品ページの【規格書・商品情報をダウンロード】【サンプル依頼・問い合わせ】機能がご利用いただけます。
「着色料」をシェアシマで検索 >
ご希望の商品が見つからない方は、シェアシマ事務局までお問い合わせください。皆さまの原料探しを全力でサポートをさせていただきます。

 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。