
代替肉とはどんな肉?大豆やきのこなど、原材料別に特徴を解説
世界中で「代替肉」のブームが到来しています。代替肉とは、その名前の示す通り、牛肉や豚肉、鶏肉などの動物の肉の代わりに、植物性原料で作られた「まるで肉のような食材」のことです。では実際に、代替肉はどのような素材から作られ、どのように利用されているのでしょうか。この記事では、代替肉の定義を確認した上で、代替肉の原材料や原材料別の使用例について解説します。この記事を読むことで、代替肉の全体像を把握し、代替肉は具体的にどのようなものであるかを理解していただけます。

 大豆ミートは、その名前の通り大豆で作られた代替肉のことです。ソイミートや大豆肉と呼ばれることもあります。大豆は別名「畑の肉」と呼ばれるほど栄養が豊富で、良質なタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルも多く含有しています。
大豆ミートは代替肉の定番であり商品の数も多く、最近はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで見かける機会も増えました。
大豆ミートは水やお湯などで戻してから利用する「乾燥タイプ」が主流ですが、すぐに使える「レトルトタイプ」や「冷凍タイプ」もあります。また、形状は主に「ミンチタイプ」「フィレタイプ」「ブロックタイプ」という3種類で、用途に応じて使い分けできます。
大豆ミートは、その名前の通り大豆で作られた代替肉のことです。ソイミートや大豆肉と呼ばれることもあります。大豆は別名「畑の肉」と呼ばれるほど栄養が豊富で、良質なタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルも多く含有しています。
大豆ミートは代替肉の定番であり商品の数も多く、最近はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで見かける機会も増えました。
大豆ミートは水やお湯などで戻してから利用する「乾燥タイプ」が主流ですが、すぐに使える「レトルトタイプ」や「冷凍タイプ」もあります。また、形状は主に「ミンチタイプ」「フィレタイプ」「ブロックタイプ」という3種類で、用途に応じて使い分けできます。

 ひよこ豆は大豆と同じくらいの大きさの丸い豆です。アジア西部が原産で、インドや欧米諸国、中近東などでは一般的によく流通しています。タンパク質が多く食物繊維が豊富で脂肪分が少ないことから、少し前から食肉に代わるヘルシーな食材として話題を集めています。
ひよこ豆は日本では馴染みの薄い豆ですが、味にクセが少ないため食べやすいのが特徴です。乾燥した状態の豆は水で戻して煮る必要がありますが、水煮されたレトルトタイプを使えば、手軽に利用できます。
ひよこ豆は大豆と同じくらいの大きさの丸い豆です。アジア西部が原産で、インドや欧米諸国、中近東などでは一般的によく流通しています。タンパク質が多く食物繊維が豊富で脂肪分が少ないことから、少し前から食肉に代わるヘルシーな食材として話題を集めています。
ひよこ豆は日本では馴染みの薄い豆ですが、味にクセが少ないため食べやすいのが特徴です。乾燥した状態の豆は水で戻して煮る必要がありますが、水煮されたレトルトタイプを使えば、手軽に利用できます。
レンズ豆とは
レンズ豆は、レンズのように平たい形状をしています。レンズ豆には緑色やオレンジ色、褐色などさまざまな色があり、3~6ミリ程度と非常に小さいことも特徴です。日本ではあまり知られていない豆ですが、欧州などでは日常的に利用されていて、特にヴィーガンやベジタリアンの人たちに親しまれています。
レンズ豆は「世界五大健康食品」の一つに数えられていて、ビタミンB群やタンパク質、鉄分、食物繊維を多く含有しています。特に、皮付きの茶色のレンズ豆には100グラム中に9.4ミリグラムの鉄分が含まれていて、これは大豆の含有量よりも多いと言われています。
 エノキートとは、エノキタケとミートを組み合わせた名前です。エノキートはエノキタケを主原料として作られた代替肉で、農業法人である株式会社小池えのき(以下、小池えのき)によって開発されました。小池えのきの本社がある長野県中野市は、日本最大のきのこの生産地として知られ、エノキタケの生産量は全国の約4割を占めます。地元の食材を使った、新しいタイプの代替肉として注目を集めています。
エノキートには、発芽大豆から作られた大豆ミート「ミラクルミート(DAIZ)」を使用しています。ミラクルミートには、大豆独特のくさみがほとんどありません。ミラクルミートにはうまみ成分「グルタミン酸」が含まれていて、エノキタケのグアニル酸を組み合わせることでうまみが格段にアップし、動物の肉に劣らない独特のうまみが実現できます。
エノキートとは、エノキタケとミートを組み合わせた名前です。エノキートはエノキタケを主原料として作られた代替肉で、農業法人である株式会社小池えのき(以下、小池えのき)によって開発されました。小池えのきの本社がある長野県中野市は、日本最大のきのこの生産地として知られ、エノキタケの生産量は全国の約4割を占めます。地元の食材を使った、新しいタイプの代替肉として注目を集めています。
エノキートには、発芽大豆から作られた大豆ミート「ミラクルミート(DAIZ)」を使用しています。ミラクルミートには、大豆独特のくさみがほとんどありません。ミラクルミートにはうまみ成分「グルタミン酸」が含まれていて、エノキタケのグアニル酸を組み合わせることでうまみが格段にアップし、動物の肉に劣らない独特のうまみが実現できます。


プラントベースミートと呼ばれることも
代替肉は、欧米諸国を中心とした健康への意識の高まりがきっかけで広がったとされています。代替肉は地球が抱える環境問題の解決や世界の人口増加に対する食料不足への対策、食の多様性への対応という側面においても大きな意味を持つと言われています。 代替肉の素材として最も有名なものは、大豆が主原料の「大豆ミート」でしょう。このほか、ひよこ豆、レンズ豆といった豆類も、代替肉の素材として注目されています。最近では、エノキタケを使った新しい代替肉「エノキート」も登場しました。いずれも「植物由来の肉」であることから、英語ではプラントベースミートと呼ばれています。フェイクミート、オルタナティブミートとはどう違う?
代替肉はプラントベースミート以外に、フェイク(偽物の)ミートやオルタナティブ(代替の)ミートと訳されることもあります。呼び方はそれぞれ異なるものの、いずれも動物の肉に見た目や風味を似せた、植物性原料から作られた食材を意味しています。代替肉のどのような特徴を強調したいのかによって、フェイクミートやオルタナティブミート、プラントベースミートという言葉が使い分けされているようです。大豆ミート:代替肉の定番でバリエーション豊富
大豆ミートとは
 大豆ミートは、その名前の通り大豆で作られた代替肉のことです。ソイミートや大豆肉と呼ばれることもあります。大豆は別名「畑の肉」と呼ばれるほど栄養が豊富で、良質なタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルも多く含有しています。
大豆ミートは代替肉の定番であり商品の数も多く、最近はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで見かける機会も増えました。
大豆ミートは水やお湯などで戻してから利用する「乾燥タイプ」が主流ですが、すぐに使える「レトルトタイプ」や「冷凍タイプ」もあります。また、形状は主に「ミンチタイプ」「フィレタイプ」「ブロックタイプ」という3種類で、用途に応じて使い分けできます。
大豆ミートは、その名前の通り大豆で作られた代替肉のことです。ソイミートや大豆肉と呼ばれることもあります。大豆は別名「畑の肉」と呼ばれるほど栄養が豊富で、良質なタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルも多く含有しています。
大豆ミートは代替肉の定番であり商品の数も多く、最近はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで見かける機会も増えました。
大豆ミートは水やお湯などで戻してから利用する「乾燥タイプ」が主流ですが、すぐに使える「レトルトタイプ」や「冷凍タイプ」もあります。また、形状は主に「ミンチタイプ」「フィレタイプ」「ブロックタイプ」という3種類で、用途に応じて使い分けできます。
あの有名ハンバーガー店やコーヒーチェーンでも
大豆ミートの需要の高まりを受けて、大豆ミートをメニューに導入する飲食店も増えています。大手ハンバーガーチェーン「モスバーガー」では「ソイパティシリーズ」と題して、大豆ミートを使ったハンバーガーのラインアップが登場しています。 また、大手コーヒーチェーン「スターバックス」はサマーシーズン第2弾として“Yori Dori Midori”をテーマにして、プラントベースという選択肢を提案。新しく加わったメニューのひとつ「スピナッチコーン&ソイパティ イングリッシュマフィン」では、肉の代わりに大豆を使ったソイパティを使用しています。
★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。
ひよこ豆の代替肉:味のクセが少なく使いやすい
ひよこ豆とは
 ひよこ豆は大豆と同じくらいの大きさの丸い豆です。アジア西部が原産で、インドや欧米諸国、中近東などでは一般的によく流通しています。タンパク質が多く食物繊維が豊富で脂肪分が少ないことから、少し前から食肉に代わるヘルシーな食材として話題を集めています。
ひよこ豆は日本では馴染みの薄い豆ですが、味にクセが少ないため食べやすいのが特徴です。乾燥した状態の豆は水で戻して煮る必要がありますが、水煮されたレトルトタイプを使えば、手軽に利用できます。
ひよこ豆は大豆と同じくらいの大きさの丸い豆です。アジア西部が原産で、インドや欧米諸国、中近東などでは一般的によく流通しています。タンパク質が多く食物繊維が豊富で脂肪分が少ないことから、少し前から食肉に代わるヘルシーな食材として話題を集めています。
ひよこ豆は日本では馴染みの薄い豆ですが、味にクセが少ないため食べやすいのが特徴です。乾燥した状態の豆は水で戻して煮る必要がありますが、水煮されたレトルトタイプを使えば、手軽に利用できます。
使用例:カレーや揚げ物、おやつにも
ひよこ豆の生産量はインドが世界一で、ベジタリアンの多いインドではカレーの具材に使われることも多く、日常的に食べられています。インドでは、ひよこ豆の外側の皮を取り除いて割った豆を「ダール」と呼び、カレーにもよく利用されています。また、ひよこ豆を粉末にした「ベサン粉」は、インド風天ぷら「パコラ」をはじめ、おやつや軽食にも用いられています。 この他にひよこ豆を使った料理としては、ひよこ豆のペースト「フムス」やひよこ豆のコロッケ「ファラフェル」も有名です。 ひよこ豆についてはこちら:ひよこ豆(ガルバンゾー)とは?ヴィーガンに人気なおすすめレシピを紹介レンズ豆の代替肉:ひき肉代わりとして使える
レンズ豆とは
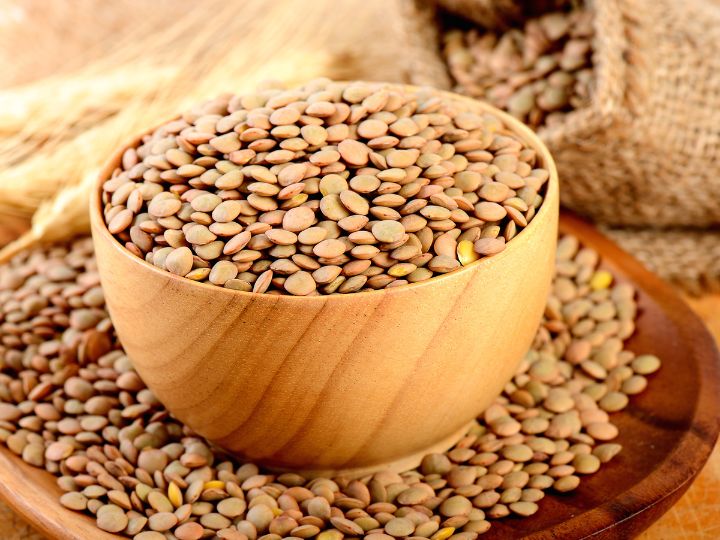
レンズ豆は、レンズのように平たい形状をしています。レンズ豆には緑色やオレンジ色、褐色などさまざまな色があり、3~6ミリ程度と非常に小さいことも特徴です。日本ではあまり知られていない豆ですが、欧州などでは日常的に利用されていて、特にヴィーガンやベジタリアンの人たちに親しまれています。
レンズ豆は「世界五大健康食品」の一つに数えられていて、ビタミンB群やタンパク質、鉄分、食物繊維を多く含有しています。特に、皮付きの茶色のレンズ豆には100グラム中に9.4ミリグラムの鉄分が含まれていて、これは大豆の含有量よりも多いと言われています。
使用例:カレーや煮込み料理、サラダに
レンズ豆はインドやネパールではカレーの具材として、イタリアやフランスなどの国では煮込み料理やサラダなどによく使われています。代替肉としての使い方として、レンズ豆は粒が小さいので、ひき肉のような感覚で利用することができます。例えば、ハンバーグを作る際にレンズ豆で代用する方法があります。 レンズ豆には特有の匂いがあるので、気になる場合は、スパイスを加えたり濃い味付けをしたりするのがおすすめです。レンズ豆は水を吸収しやすいため、あらかじめ水で戻す必要がなく、料理にそのまま使うことができるのも魅力です。エノキート:キノコの旨味でおいしさ追求
エノキートとは
 エノキートとは、エノキタケとミートを組み合わせた名前です。エノキートはエノキタケを主原料として作られた代替肉で、農業法人である株式会社小池えのき(以下、小池えのき)によって開発されました。小池えのきの本社がある長野県中野市は、日本最大のきのこの生産地として知られ、エノキタケの生産量は全国の約4割を占めます。地元の食材を使った、新しいタイプの代替肉として注目を集めています。
エノキートには、発芽大豆から作られた大豆ミート「ミラクルミート(DAIZ)」を使用しています。ミラクルミートには、大豆独特のくさみがほとんどありません。ミラクルミートにはうまみ成分「グルタミン酸」が含まれていて、エノキタケのグアニル酸を組み合わせることでうまみが格段にアップし、動物の肉に劣らない独特のうまみが実現できます。
エノキートとは、エノキタケとミートを組み合わせた名前です。エノキートはエノキタケを主原料として作られた代替肉で、農業法人である株式会社小池えのき(以下、小池えのき)によって開発されました。小池えのきの本社がある長野県中野市は、日本最大のきのこの生産地として知られ、エノキタケの生産量は全国の約4割を占めます。地元の食材を使った、新しいタイプの代替肉として注目を集めています。
エノキートには、発芽大豆から作られた大豆ミート「ミラクルミート(DAIZ)」を使用しています。ミラクルミートには、大豆独特のくさみがほとんどありません。ミラクルミートにはうまみ成分「グルタミン酸」が含まれていて、エノキタケのグアニル酸を組み合わせることでうまみが格段にアップし、動物の肉に劣らない独特のうまみが実現できます。
使用例:ハンバーグ
エノキートを使った代表的な料理は、ハンバーグです。原材料は、エノキタケとタマネギ、大豆ミート、パン粉、調味料。原材料の半分以上が、エノキタケとタマネギです。5ミリ程度のみじん切りにしたエノキタケを使用することで、肉によく似た食感が生まれます。エノキタケは加熱すると独特のぬめりが出るため、つなぎの代わりになるという点からハンバーグに使うのに適しています。 エノキートのハンバーグは合いびき肉を使った通常のものに比べて、脂質やカロリーが少なく食物繊維が多いとされています。大豆ミートを使用しているため、タンパク質の量は通常のハンバーグとほとんど変わりません。ヘルシーでありながらタンパク質がしっかり摂取できるので、ベジタリアンやヴィーガンの人たちだけでなく、健康への意識が高い人にも支持されています。まとめ
世界中で需要が高まっている、代替肉。代替肉と一口に言ってもその種類は多く、今回紹介した4種類以外にもさまざまなタイプがあります。 代替肉には私たちの健康維持や地球の環境保全につながるメリットがある一方で、原材料の調達や製造プロセス次第では、環境に負荷を与える可能性もあると言われています。今後、こうしたデメリットにどのように対応していくのかが課題でしょう。代替肉の分野は成長過程にあり、これからの展開に注目したいです。 https://shareshima.com/274

 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。











