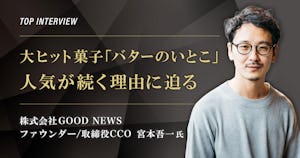知らないとまずい?!タンパク質危機。20XX年までに肉や魚が足りなくなる?
地球の人口増加や環境問題により、食肉などのタンパク質が不足するのが「タンパク質危機」です。私たちの食卓に影響するかもしれない世界規模での課題であるにもかかわらず、一般にはそれほど広く認知されていません。こちらの記事では、タンパク質危機とはどのような問題かを解説すると共に、タンパク質危機を避けるための4つの選択肢について説明します。タンパク質危機という問題が生じている理由から取りうる対応策までを紹介し、プラントベースフードなどがにわかに注目を浴びている背景をお伝えしていきます。

タンパク質危機は、世界人口の急速な増加に由来する問題です。まずはその背景的な事情からみていきましょう。
日本では、出生率の低下に伴い若年層の人口が減少する「少子化」が急速に進んでいます。そのためあまり実感がわきませんが、一方で世界の人口は増え続けている状況です。国連の調査によれば、世界の人口は現在約80億人であるところ、2030年には約85億人、2050年には約98億人、2100年には約112億人になると推定されています。
世界規模での人口増加に伴って、近い将来、牛や豚、鶏などの畜産によるタンパク質が不足すると予測されています。この予測は「タンパク質危機」と呼ばれていて、欧米諸国を中心に話題になっています。現状のままだと早ければ2025年から2030年ごろまでに需要と供給のバランスが崩れ始めると言われています。
人間の身体を構成するのは、水分が約60%、タンパク質が約15~20%とされています。つまり、タンパク質は水分を除いて体の重量の約半分を構成する、生きていく上で大切な栄養素です。欧米では「プロテインチャレンジ2040」と題したコンソーシアムが立ち上がり、その中から複数のプロジェクトが始動しています。タンパク質危機をどう乗り越えていくのかは、人類が生きていく上で極めて重要な課題です。
タンパク質危機を回避するために、世界中でさまざまな検討が行われています。ここでは、その中から代替肉と培養肉、昆虫食、藻類という4つの選択肢について解説します。
代替肉とは、牛肉や豚肉、鶏肉などの動物の肉の代わりに、植物性原料で作られた「肉のような食材」のことです。欧米諸国を中心とした健康への意識の高まりがきっかけで広がったとされていて、別名「プラントベースミート」と呼ばれることもあります。
代替肉の素材として最も有名なものは、大豆が主原料の「大豆ミート」でしょう。有名ハンバーガー店やコーヒーチェーンでも大豆ミートを使ったメニューが登場し、話題になっています。このほか、ひよこ豆、レンズ豆といった豆類も、代替肉の素材として注目されています。最近では、エノキタケを使った新しい代替肉「エノキート」も登場するなど、さまざまな研究・開発が進められています。
培養肉は、牛などの動物から取った少量の細胞を、再生医療の技術により体外で増やして作られます。プラントベースの代替肉とは異なり「本物の肉を使った代用品」です。従来の食肉の生産方法と比べて、飼育・繁殖する過程における動物へのストレスや環境への負荷が少ないとされています。こうした特徴から、別名「クリーンミート」と呼ばれることもあります。
培養肉は、2013年にオランダの研究者が培養ミンチ肉を作ったのがその始まりです。日本でも培養肉の研究が進められていて、2019年には世界で初めてサイコロステーキ状の培養肉を作ることに成功しました。大きな肉を作るための技術の開発など乗り越えなくてはならないハードルが多いものの、持続可能な食材という意味で期待が寄せられています。
昆虫食とは、コオロギなどの昆虫を原料にした食品のことです。大豆ミートなどのプラントベースフードは植物性のタンパク質しか得られないのに対して、昆虫食の場合、肉や魚と同様、必須アミノ酸である動物性タンパク質を得ることができます、また、昆虫食は飼育・加工に必要なスペースや資源が最小限で済み、環境負荷が低いというメリットもあります。
日本にも貴重なタンパク源として昆虫を食べる地域の文化が残っていますが、世界で食べられている昆虫は1900種類にも及ぶとされ、アジアやアフリカ、中南米を中心に昆虫を食べる食文化が見られます。昆虫食には食品の安全性や見た目への抵抗感といった課題があるものの、環境負荷の少ないサステナブルな食材として注目を集めています。
細胞分裂をして増殖する藻類はタンパク質含有量が50~75%であり、新たなタンパク質源としての可能性を持っています。藻類は良質なタンパク質だけでなく、炭水化物や脂質、ビタミン、ミネラルなども豊富に含まれています。現在市場に流通しているのはタンパク質が豊富に含まれるクロレラやスピルリナで、藻類をそのまま乾燥させて粉末状にしたものが主流です。
藻類は栄養価が豊富であるものの、藻類を乾燥した粉末は独特の匂いがあることや、藻類バイオマスの生産コストが肉や大豆に比べて価格が高いことなどから、タンパク質源としてはこれまで積極的に利用されていませんでした。しかし、近い将来に訪れるとされるタンパク質危機を前に、藻類の利活用が見直され始めています。

世界の人口増加に伴って、近い将来訪れると言われているタンパク質危機。この記事では、タンパク質危機を回避するために私たちが取りうる選択肢として、代替肉、培養肉、昆虫食、藻類の4つを紹介しました。食品としての安全性や抵抗感、生産コストなど、それぞれに乗り越えるべき障壁はありますが、タンパク質危機を避けるために、世界中でさまざまな研究・開発が行われています。これまでの常識にとらわれない、新しい食の選択肢が求められていると言えそうです。

タンパク質危機(タンパク質クライシス)とは
タンパク質危機は、世界人口の急速な増加に由来する問題です。まずはその背景的な事情からみていきましょう。
少子化真っ只中の日本。でも世界の人口は?
日本では、出生率の低下に伴い若年層の人口が減少する「少子化」が急速に進んでいます。そのためあまり実感がわきませんが、一方で世界の人口は増え続けている状況です。国連の調査によれば、世界の人口は現在約80億人であるところ、2030年には約85億人、2050年には約98億人、2100年には約112億人になると推定されています。
2030年までにタンパク源が足りなくなる恐れ
世界規模での人口増加に伴って、近い将来、牛や豚、鶏などの畜産によるタンパク質が不足すると予測されています。この予測は「タンパク質危機」と呼ばれていて、欧米諸国を中心に話題になっています。現状のままだと早ければ2025年から2030年ごろまでに需要と供給のバランスが崩れ始めると言われています。
人間の身体を構成するのは、水分が約60%、タンパク質が約15~20%とされています。つまり、タンパク質は水分を除いて体の重量の約半分を構成する、生きていく上で大切な栄養素です。欧米では「プロテインチャレンジ2040」と題したコンソーシアムが立ち上がり、その中から複数のプロジェクトが始動しています。タンパク質危機をどう乗り越えていくのかは、人類が生きていく上で極めて重要な課題です。
タンパク質危機を避けるための4つの選択肢
タンパク質危機を回避するために、世界中でさまざまな検討が行われています。ここでは、その中から代替肉と培養肉、昆虫食、藻類という4つの選択肢について解説します。
代替肉
代替肉とは、牛肉や豚肉、鶏肉などの動物の肉の代わりに、植物性原料で作られた「肉のような食材」のことです。欧米諸国を中心とした健康への意識の高まりがきっかけで広がったとされていて、別名「プラントベースミート」と呼ばれることもあります。
代替肉の素材として最も有名なものは、大豆が主原料の「大豆ミート」でしょう。有名ハンバーガー店やコーヒーチェーンでも大豆ミートを使ったメニューが登場し、話題になっています。このほか、ひよこ豆、レンズ豆といった豆類も、代替肉の素材として注目されています。最近では、エノキタケを使った新しい代替肉「エノキート」も登場するなど、さまざまな研究・開発が進められています。
培養肉
培養肉は、牛などの動物から取った少量の細胞を、再生医療の技術により体外で増やして作られます。プラントベースの代替肉とは異なり「本物の肉を使った代用品」です。従来の食肉の生産方法と比べて、飼育・繁殖する過程における動物へのストレスや環境への負荷が少ないとされています。こうした特徴から、別名「クリーンミート」と呼ばれることもあります。
培養肉は、2013年にオランダの研究者が培養ミンチ肉を作ったのがその始まりです。日本でも培養肉の研究が進められていて、2019年には世界で初めてサイコロステーキ状の培養肉を作ることに成功しました。大きな肉を作るための技術の開発など乗り越えなくてはならないハードルが多いものの、持続可能な食材という意味で期待が寄せられています。
昆虫食
昆虫食とは、コオロギなどの昆虫を原料にした食品のことです。大豆ミートなどのプラントベースフードは植物性のタンパク質しか得られないのに対して、昆虫食の場合、肉や魚と同様、必須アミノ酸である動物性タンパク質を得ることができます、また、昆虫食は飼育・加工に必要なスペースや資源が最小限で済み、環境負荷が低いというメリットもあります。
日本にも貴重なタンパク源として昆虫を食べる地域の文化が残っていますが、世界で食べられている昆虫は1900種類にも及ぶとされ、アジアやアフリカ、中南米を中心に昆虫を食べる食文化が見られます。昆虫食には食品の安全性や見た目への抵抗感といった課題があるものの、環境負荷の少ないサステナブルな食材として注目を集めています。
藻類
細胞分裂をして増殖する藻類はタンパク質含有量が50~75%であり、新たなタンパク質源としての可能性を持っています。藻類は良質なタンパク質だけでなく、炭水化物や脂質、ビタミン、ミネラルなども豊富に含まれています。現在市場に流通しているのはタンパク質が豊富に含まれるクロレラやスピルリナで、藻類をそのまま乾燥させて粉末状にしたものが主流です。
藻類は栄養価が豊富であるものの、藻類を乾燥した粉末は独特の匂いがあることや、藻類バイオマスの生産コストが肉や大豆に比べて価格が高いことなどから、タンパク質源としてはこれまで積極的に利用されていませんでした。しかし、近い将来に訪れるとされるタンパク質危機を前に、藻類の利活用が見直され始めています。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。
まとめ
世界の人口増加に伴って、近い将来訪れると言われているタンパク質危機。この記事では、タンパク質危機を回避するために私たちが取りうる選択肢として、代替肉、培養肉、昆虫食、藻類の4つを紹介しました。食品としての安全性や抵抗感、生産コストなど、それぞれに乗り越えるべき障壁はありますが、タンパク質危機を避けるために、世界中でさまざまな研究・開発が行われています。これまでの常識にとらわれない、新しい食の選択肢が求められていると言えそうです。

 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。