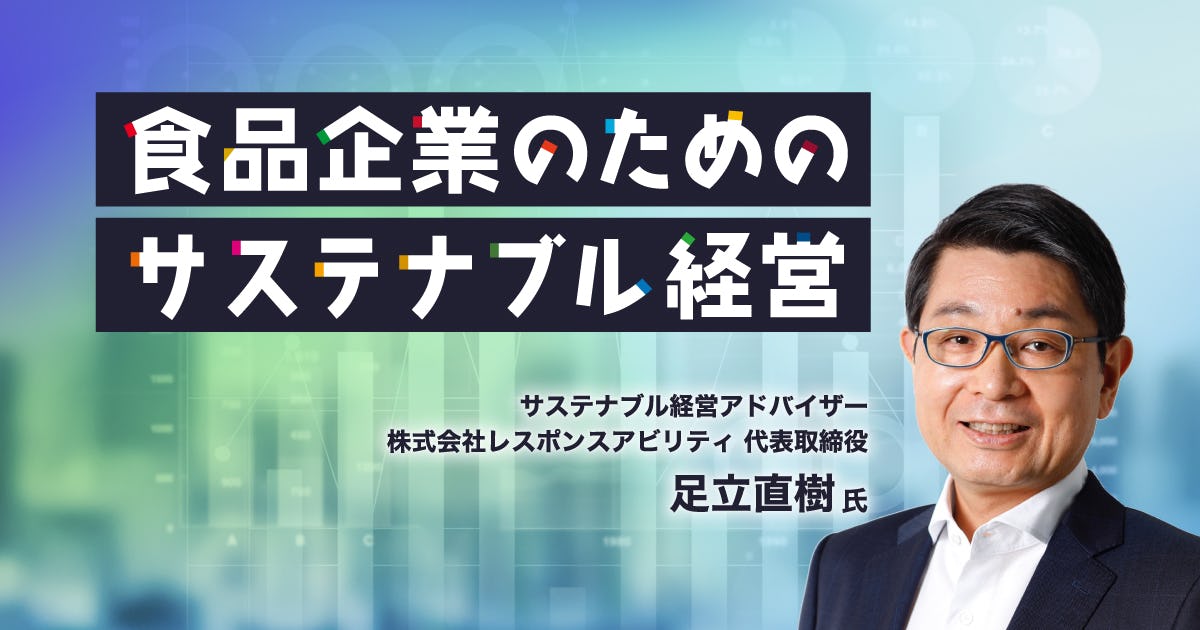
実は宝の山!? 未利用魚の可能性【食品企業のためのサステナブル経営(第25回)】
前回の記事を読む:対岸の火事ではない水不足【食品企業のためのサステナブル経営(第24回)】
未利用魚(みりようぎょ)という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 未利用とは、捕獲したのに利用されていないということです。一般的な「食ロス」のように加工や消費の途中で廃棄されたのではなく、そもそも流通にすら乗らないという大変もったいないものです。しかも驚くのはその量です。一般には漁獲量の約3割が未利用魚と言われます。これはまったく利用されずに「廃棄される」量で、そんなに無駄になっているのかと驚きます。
けれども本当に驚くにはまだ早いのです。漁獲されたのに、食用には使われず、ペットフードや飼料用などに回される広義の未利用魚も含めると、実際には日本の漁獲量のなんと半分以上が未利用魚で、本来の価値を発揮できていない可能性があるというのです。これは本当にもったいない話ですし、水産資源の持続可能性を考えると、非常に深刻な問題です。こんなやり方を続けていたら、将来の漁業に大きなツケを残すことになるでしょう。
魚種を問わず、最近は水産資源量が恐ろしく減ってしまっているというのに、とてつもない無駄であり、とても「持続可能」とは言えない状況です。第一に魚の獲り方を見直すべきであることは言うまでもありませんが、それは水産業の課題です。今回はそうは言っても発生してしまっている「未利用魚」をどう活用するかという、消費側の話をしたいと思います。なぜなら、これは食品メーカーにとっては大きなチャンスだからです。未利用魚の有効活用は、食品ロス削減やコスト削減だけでなく、新たな商品開発やブランド価値の向上にもつながるのです。
そもそも未利用魚とは?
 足立直樹
足立直樹
サステナブル経営アドバイザー。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役。東京大学理学部卒業、同大学院修了、博士(理学)。植物生態学の研究者としてマレーシアの熱帯林で研究をし、帰国後、国立環境研究所を辞して独立。その後は、企業と生物多様性およびサステナブル調達の日本の第一人者として、日本の食品会社、飲料会社、流通会社、総合商社等の調達を持続可能にするプロジェクトに数多く参画されています。2018年に拠点を東京から京都に移し、地域企業の価値創造や海外発信の支援にも力を入れていて、環境省を筆頭に、農水省、消費者庁等の委員を数多く歴任されています。




