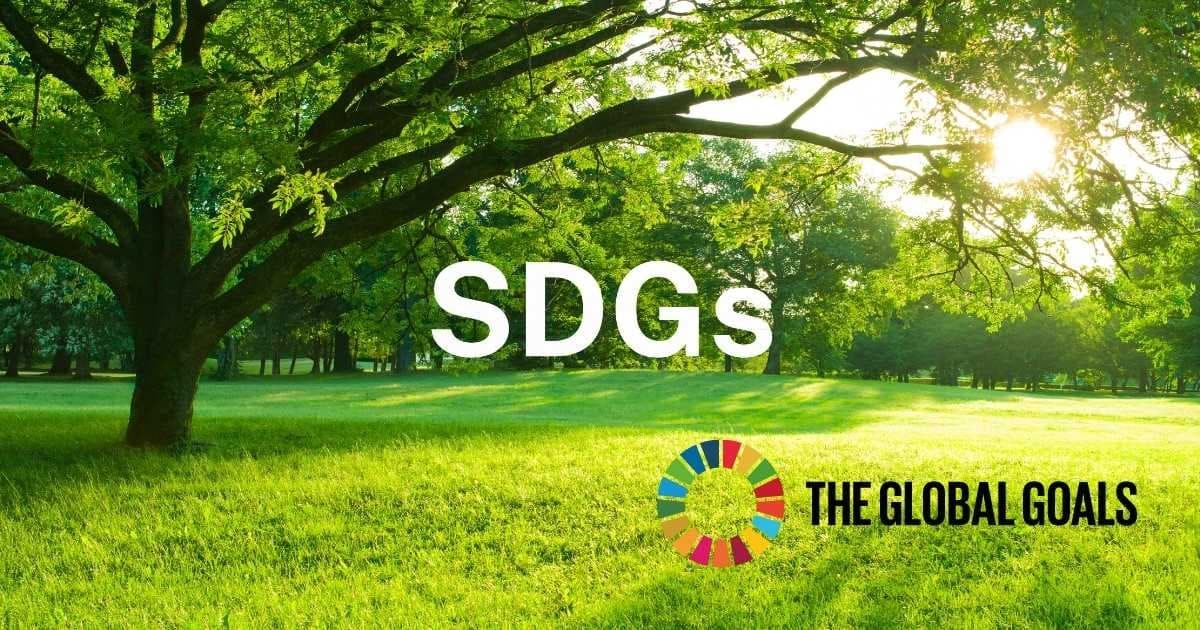
SDGsって何の略?知ればその意味や目標がわかる!企業やNPOの取り組み事例も解説
近年、SDGs(エス・ディー・ジーズ)という言葉が多くの場面で使われるようになり、食品業界ではさまざまな取り組みが推進されています。一方で、何となく言葉は知っていても、正確な意味や目指す姿がわからないという声も少なくありません。
そこでこの記事では、SDGsが掲げる17の目標や169のターゲットについて説明し、さらには企業やNPO/NGOの取り組み事例を知っていただくことで、SDGsの目指す姿を解説していこうと思います。
SDGsは持続可能な開発目標のこと
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月の国連サミットにおいて決められた世界共通の目標です。2016年から2030年までの15年間の開発の指針として「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、その中心となる開発目標をSDGsと呼んでいます。
ちなみに、SDGsの前身である「MDGs(エムディージーズ)」では、2015年までの開発目標として8つのゴールを掲げていました。この目標が達成期限を迎えたことを受けて、次に決定されたのがSDGsです。
SDGsの17の目標とは
SDGsでは、17の大きな目標が設定されています。その目標とは、「1.貧困をなくそう」「2.飢餓をゼロに」「3.すべての人に健康と福祉を」「4.質の高い教育をみんなに」「5.ジェンダー平等を実現しよう」「6.安全な水とトイレを世界中に」「7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに」「8.働きがいも経済成長も」「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」「10.人や国の不平等をなくそう」「11.住み続けられるまちづくりを」「12.つくる責任 つかう責任」「13.気候変動に具体的な対策を」「14.海の豊かさを守ろう」「15.陸の豊かさも守ろう」「16.平和と公正をすべての人に」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」です。
貧困や飢餓といえば「開発途上国が対象」というイメージがあるかもしれませんが、日本の子どもの「7人に1人が貧困」とも言われていて、日本においても重要なテーマとなっています。17の目標の特徴は、開発途上国だけでなく先進国も対象にしていることです。気候変動や働きがい、経済成長など多岐に渡るテーマが盛り込まれています。
SDGsの169のターゲットとは
17の目標を達成するために設定されているのが、169のターゲットです。すべてのターゲットは、農林水産省のサイトから確認できます。一つの目標に対して平均して10個程度のターゲットが存在する計算になります。
ターゲットの内容としては、具体的な指標を示しているものもあれば、漠然とした表現のものもあります。そこで、169のターゲットをより具体化して数値目標を盛り込んだ232の指標が策定されました。SDGsの全体像として、17の目標、169のターゲット、232の指標で構成されています。
SDGsの大きな特徴は、目標を掲げるだけでなく達成状況を定期的にモニタリングすることにあります。「国連ハイレベル政治フォーラム」という枠組みを使って、毎年7月ごろに各国の進捗状況を共有しています。
食品企業が取り組む事例
SDGsの17の目標は食品業界食品業界に関わるものも多く、さまざまな取り組みが推進されています。たとえば、「2.飢餓をゼロに」では、アジアやアフリカを中心に深刻化している飢餓や栄養不良といった問題解決に取り組む企業や、「12.つくる責任 つかう責任」では、従来の大量生産・大量消費から持続可能な仕組みへと変化していく企業の姿もあります。「4.質の高い教育をみんなに」では、大手食品産業を中心に食育や環境教育が実践されています。
ここでは、食品業界における「企業が取り組むSDGs」として、いくつか事例をご紹介します。
ハナマルキ
ハナマルキ株式会社は、イオンアグリ創造株式会社とのコラボレーションで「液体塩こうじ×青いトマトプロジェクト」を2022年7月にスタートさせました。食品ロスの削減につながるだけでなく、「青いトマトがおいしく変身する」と多方面から注目を集めています。
このプロジェクトは、これまで廃棄処分されてきた青いトマトを液体塩こうじと組み合わせて、青いトマトの特徴を生かしたおいしい料理に変身させるというもの。イオン農場ECサイトにて、液体塩こうじと青いトマト、ミニレシピリーフレット付のセット販売を行っています(1セットにつき液体塩こうじ1本と青いトマト6個入りで税込1000円、送料別)。
関連記事:青いトマトがおいしく大変身!液体塩こうじでつくる食品ロスのない社会〜醸造の奥深さを知るみそメーカーだからできるSDGsプロジェクト〜
森永乳業
森永乳業株式会社では「笑顔を未来につなぐプロジェクト」と題して、サステナブルな社会の実現に向けて、さまざまなプロジェクトを展開しています。プロジェクトの紹介サイトでは、クイズやゲーム、漫画などのコーナーがあり、SDGsの意味や森永乳業の取り組みを子どもから大人まで楽しく理解できます。
同社の商品では、2020年度から「認証カカオ豆」を使用し、カカオ豆を生産する農家の支援や貧困問題、地球温暖化などの解決に取り組んでいます。また商品の包装には、FSC認証紙や再生紙、環境に配慮した紙を使用し、森林資源の保護を目指しています。この他、お菓子の原材料となるパーム油や印刷に使うインキなども環境にやさしいものを使うよう配慮しています。
敷島製パン
敷島製パン株式会社(Pasco)では「ゆめちから栽培研究プログラム」を行っています。このプログラムは、中学・高校生が自ら国産小麦を育て、収穫した小麦でパンを作ることにより、日々食べているものや人とのつながりに対する意識や関心を高めることを目指しています。
日本の小麦の食料自給率は約15%とされ、特にパン用小麦は、そのほとんどを輸入に頼っています。こうした状況を改善すべく開発されたのが「ゆめちから」という品種で、日本の高温多湿な環境でも栽培しやすいという特徴があります。本プログラムには、日本の小麦の生産量を増やして日本の小麦で作ったパンを広めるという想いも込められています。
NPO/NGOが取り組む事例
SDGsに取り組んでいるのは、企業だけではありません。ここではNPO/NGOの取り組みとして、TABLE FOR TWOの事例を紹介します。
TABLE FOR TWO
NPO法人「TABLE FOR TWO」は、飢餓と飽食という世界規模で起きている食の不均衡を解決することをミッションにした団体です。2007年に日本で設立して以来、先進国で健康的な食生活を提供しながら、開発途上国の子どもたちに学校給食を届ける活動を行っています。
「TFTプログラム」は、先進国で食事やサービスを受け取ると、その売上の一部が寄付金となって、開発途上国の学校給食になるというものです。この仕組みは大企業の社員食堂などにも採用され、設立から15年間で学校給食数は累計9,000万食以上も届けられています。
まとめ
食品業界では、多様な視点からSDGsの取り組みが行われています。取り組み事例を見ていると、食の分野には、貧困や飢餓、健康状態の改善だけでなく、環境保全やまちづくり、教育の質の向上、パートナーシップなどさまざまな可能性があると感じました。
実は、国連サミットで193ヵ国が全会一致で採択した文書の正式名称は、SDGsではなく「Transforming Our World(我々の世界を変革する)」とされています。SDGsは、この文書の一部に書いてあったものです。
SDGsの本質を考えたとき、「食には世界を変革するための大きな可能性がある」と言っても、過言ではないでしょう。食に関わる者として、あらゆる主体が自ら考え、取り組んでいくことが大切なのかもしれません。
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。










