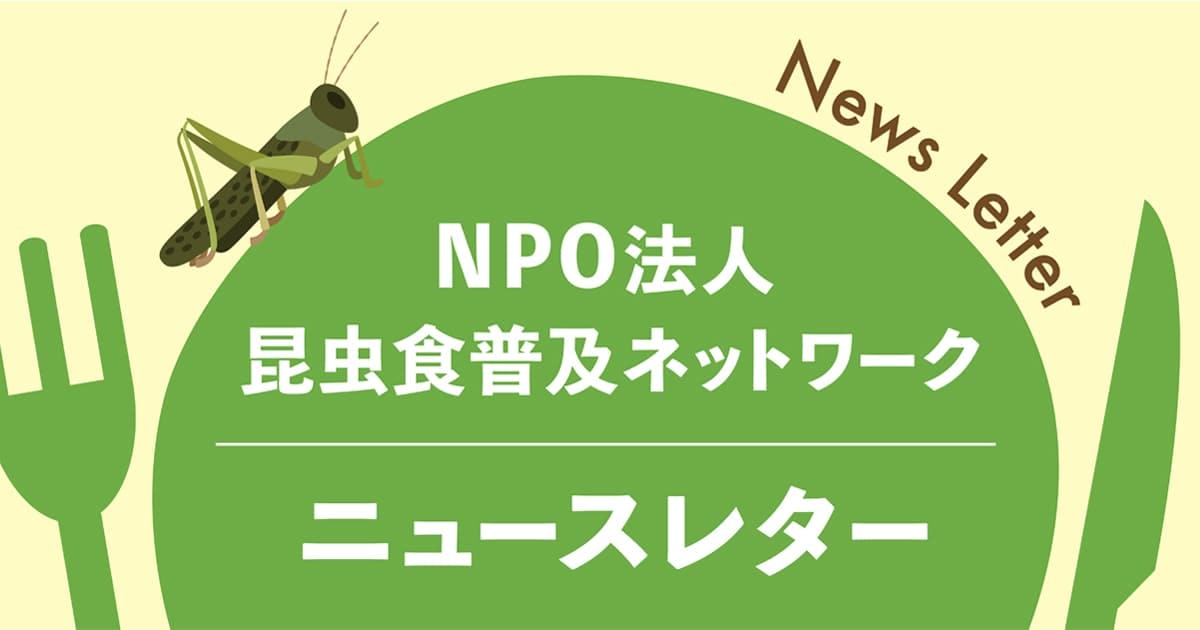
昨今のコオロギ食論争を巡って(2)【昆虫食普及ネットワーク|ニュースレターから】
前回の記事を読む:昨今のコオロギ食論争を巡って(1)【昆虫食普及ネットワーク|ニュースレターから】
3.なぜコオロギ養殖だけに国が支援し助成金を出しているのでしょうか
コオロギ食事業へ6兆円は間違いです。日本政府が策定した「SDGsアクションプラン2021」の予算6.5兆円が一人歩きしたのでしょう。重点事項に「コオロギ食事業」という表記はありません。
農研機構のムーンショット型農林水産研究開発事業の関連予算は1億6千万円です。「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」というコオロギなど昆虫食研究テーマはありますが、これはコオロギの養殖事業に特化した補助金ではありません。
農水省の予算はトータルで2兆2千億円です。そのうちのフードテック関連の予算は3千万円ですが、これは昆虫食に限った補助金ではありません。令和4年度予算から出ている事業に昆虫に関するものがありますがこれは食用ではなく飼料です。
コオロギなど昆虫が家畜に代わる唯一の代替タンパク質ではありません。代替たんぱく質には大豆など植物由来、細胞培養、発酵由来、昆虫食などがあり、さまざまな食品の開発が進められています。食文化や好みの違いがあるので多様な選択肢があったほうがいいでしょう。
なぜいま主にコオロギが養殖されているかというと、雑食なので餌の選択肢がいろいろあることです(穀物や野菜くず、残飯など)。日本のコオロギと違って養殖物は熱帯産なので通年飼育が可能なこともあります。飼育が容易で、発育日数が短く(1〜1.5か月)、サイズも大きいことです。
4.まだまだ高い普及の壁を取り除くにはどうしたらいいでしょうか
昆虫を食べられない人から理由を聞くと「姿・形がグロテスク」「理屈抜きで拒否する」「餓死しても食べたくない」が最も多く、〝嫌悪感〟が心理的な大きな壁になっています。「不味食物群」「危険食物群」「不適切食物群」の3つを併せ持つ食物群を「嫌悪食物群」と言い、コオロギなど昆虫がまさに「嫌悪食物群」に該当します。
雑食性の人間は、食物新奇性恐怖の人が多数で、食物新奇性嗜好の人は少数です。おなじ雑食性のネズミでも、飼育用の餌しか食べていないネズミにチーズを与えても怖がって後ずさりするという実験結果があります。「美味しくて安全」が普及の決め手です。受容傾向(食物新奇性嗜好)の強い消費者への働きかけが重要です。そうした昆虫食に関心のある人たちに美味しく食べてもらうことで、普及の壁も乗り越えられると思います。
東南アジアやアフリカなど熱帯地域ではコオロギは日常食べられている普通の食材です。食べる、食べないは個人の自由ですが、コオロギ食を否定することはその国や地域の食文化を否定することにならないでしょうか。2013年のFAO報告は、地域に根差した昆虫食文化を環境面や栄養面から評価し、維持・拡大することで、貧困と栄養不足を解消する狙いがあります。
(内山昭一/NPO法人昆虫食普及ネットワーク理事長)
ニュースレターは、NPO法人昆虫食普及ネットワークの公式HPで配信中です。






