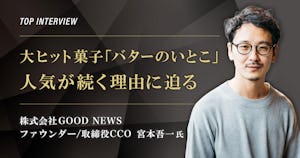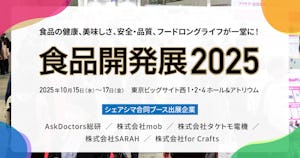【登壇レポ】製造段階の食ロスに価値を、アップサイクルという選択肢【 ifia JAPAN セミナー】
シェアシマを運営するICS-net株式会社は、東京ビッグサイト(南1・2ホール)にて5月19日まで3日間開催されたifia JAPAN 2023(第28回国際食品素材/添加物展・会議)に出展。ブース出展したほか、主催者企画セミナーに登壇し、ICS-net株式会社 アップサイクル推進室 室長 菊地 由華が「食品製造段階で発生する食品ロスを活用!新たな価値創出『アップサイクル』について」をテーマに講演しました。
記事の要旨:
食料自給率が38%しかない日本は、海外からの食材輸入に大きく依存しており、食品製造過程で年間121万トンの食品ロスが発生しています。この問題に取り組むシェアシマは、余剰原料を再利用する「アップサイクル」を促進するためのサービスを提供しています。アップサイクルとは、通常であれば廃棄されてしまう原料を活用して、新たな価値ある商品を作り出すという考え方です。主に未利用の原料や製造過程で出じる端材を活用して新たな商品を作り出しています。これらの取り組みにより、食品ロスの削減と新たな商品開発を推進し、食品産業の持続可能な未来を構築しています。
値上がりする原料、ロスが生じる矛盾

日本の食料自給率の低さと製造段階に生じる食品ロスの問題に焦点を当てるシェアシマは、食品製造の持続可能なサプライチェーンの構築を推進しています。
日本の自給率(カロリーベース)はわずか38%で、多くの食材が海外から輸入されています。しかし、一部の海外サプライヤーからは日本への販売をためらう声もあり、日本の食品産業に大きな課題が突きつけられています。食品製造の過程で生じる食品ロスは約121万トンあるとされていて、これは日本の食品ロス全体(522万トン)のうちの23%。決して無視できない数字となっています。
シェアシマは、食品ロス削減を推進するとともに、余剰原料を生まれ変わらせる「アップサイクル」を促進するサービスを提供しています。その一つが、食品原料のサプライヤーメーカーが余剰となった原料を掲載できる[専用サイト(シェアシマアップサイクル特集)]です。これにより、食品メーカーが余剰原料を利用できる仕組みができて、食品ロスを減らすことが期待できます。
シェアシマは食品原料のサプライヤーと食品メーカーを直接つなぐサービスも提供しています。これにより、新商品開発や他の業務に時間を割くことができ、食品メーカー全体の活性化を目指しています。
シェアシマは現在、約2600のユーザーを有しており、2026年には2万5000のユーザーが参加することを目指しています。こうして構築された食品企業のプラットフォームは、食品ロス削減とアップサイクル推進を通じて、日本の食品産業の持続可能な未来を構築するための一歩となります。
アップサイクルフードで“余剰”を“価値”へ

アップサイクル事業は、廃棄される可能性のある原料を有効利用し、新たな価値を生み出す活動です。「リサイクル」が製品を原料に戻してから新たに製品を作るのに対し、「アップサイクル」は原料そのものを活かして、付加価値を向上させる新製品を創出します。
このアップサイクルの可能性を秘めた食品の原料は大きく三つに分けられます。一つは「未利用原料」、二つ目は「残渣」(皮や絞りかすなど)、そして最後に製品を作る工程で出てしまう「端材」です。私たちは、これらの原料を活用し、新たな商品を作り出す事業を展開しています。
具体的な実績として、私たちは昨年度、シェアシマのサイトを介して1トンの食品ロス削減に寄与しました。この数字は未利用の食品の積み重ねがあって初めて成り立つもので、これをさらに増やしていきたいと考えています。
さらに、私たちはアップサイクル商品の企画及び開発の推進も行っています。例えば、昨年度には長野市と共同でアップサイクル商品を発売しました。一つは、信州福味鶏のレバーとハツを使った缶詰です。これは通常余剰となる部位を有効活用し、新たな商品を創出した成功例となります。
また、ウエハースを使ったビールも開発しました。これは土産品製造会社が生成する端材をアップサイクルビール製造企業につなぎ、新たな商品を開発した事例です。これらの開発は、食品ロス削減だけでなく、新たなビジネスチャンスを創出する可能性を秘めています。
私たちの取り組みはこれからも続きます。余っている原料や商品化が困難なものがあれば、私たちにぜひご相談ください。食品ロスの削減と新たな商品開発の可能性を共に追求してまいります。