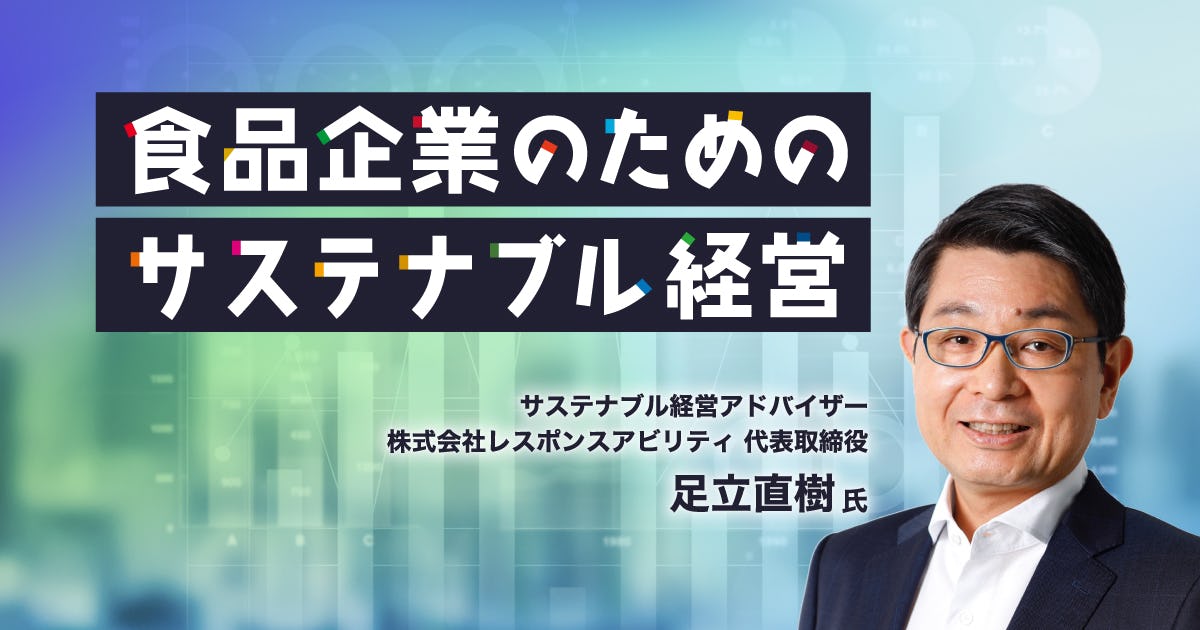
これで問題解決?!ウナギの完全養殖【食品企業のためのサステナブル経営(第9回)】
前回の記事を読む:アニマルウェルフェアが人間にも役立つわけ【食品企業のためのサステナブル経営(第8回)】
数週間前に、近畿大学がニホンウナギの完全養殖に成功したというニュース(※1)が流れました。これを聞いて、「えっ、ウナギって養殖じゃなかったの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。あるいは、「完全養殖」という言葉に気がついた方は、「完全養殖は普通の養殖とどう違うのだろう?」と思われたかもしれません。
完全養殖とは、養殖した親から生まれた卵由来の稚魚を養殖し、養殖環境下で繁殖サイクルが完全に回るようにできることです。一方で、通常の養殖ウナギの場合、人工養殖といっても稚魚は自然から採取した天然のシラスウナギであり、結局は貴重な自然の資源に依存しているのです。完全養殖ができるようになれば、天然のウナギ資源を損なうことなくウナギを利用することが可能になりますから、水産物の持続可能性のためには非常に大きな意味があるのです。
※1 参考:ニホンウナギの完全養殖に大学として初めて成功 養殖用種苗(稚魚)としての実用化をめざし、今後さらに研究を継続
「完全養殖」で、ウナギが今より安くなる?
 足立直樹
足立直樹
サステナブル経営アドバイザー。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役。東京大学理学部卒業、同大学院修了、博士(理学)。植物生態学の研究者としてマレーシアの熱帯林で研究をし、帰国後、国立環境研究所を辞して独立。その後は、企業と生物多様性およびサステナブル調達の日本の第一人者として、日本の食品会社、飲料会社、流通会社、総合商社等の調達を持続可能にするプロジェクトに数多く参画されています。2018年に拠点を東京から京都に移し、地域企業の価値創造や海外発信の支援にも力を入れていて、環境省を筆頭に、農水省、消費者庁等の委員を数多く歴任されています。




