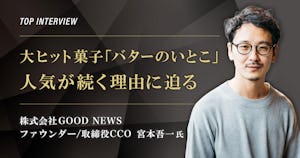食品業界の開発環境をもっと自由に—シェアシマが目指す未来【社長コラム#4】
前回の記事を読む:「捨てる」から「活かす」へ シェアシマが描く、食品業界の未来とは【社長コラム#3】
前職での苦労―理想の原料探しに一年以上
私がまだ前職で新商品開発に携わっていた頃、どうしても欲しい原料を探すのに一年以上もの時間を費やしたことがあります。新しい食感と風味を両立させるため、サンプルを取り寄せては試験を繰り返し、別のサプライヤーを探すという日々。しかし、そう簡単には見つかりませんでした。ひとたび「これだ!」という原料が見つかったと思えば、今度は大量生産ラインの調整で問題が起き、また振り出しに戻ってしまう……。
その間にかかったリソースは膨大で、開発担当者の立場からは「どうしてこんなに大変なのか」「もっと効率よく見つける方法はないのか」と頭を抱えずにはいられませんでした。
原料探しが抱える構造的な課題
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。