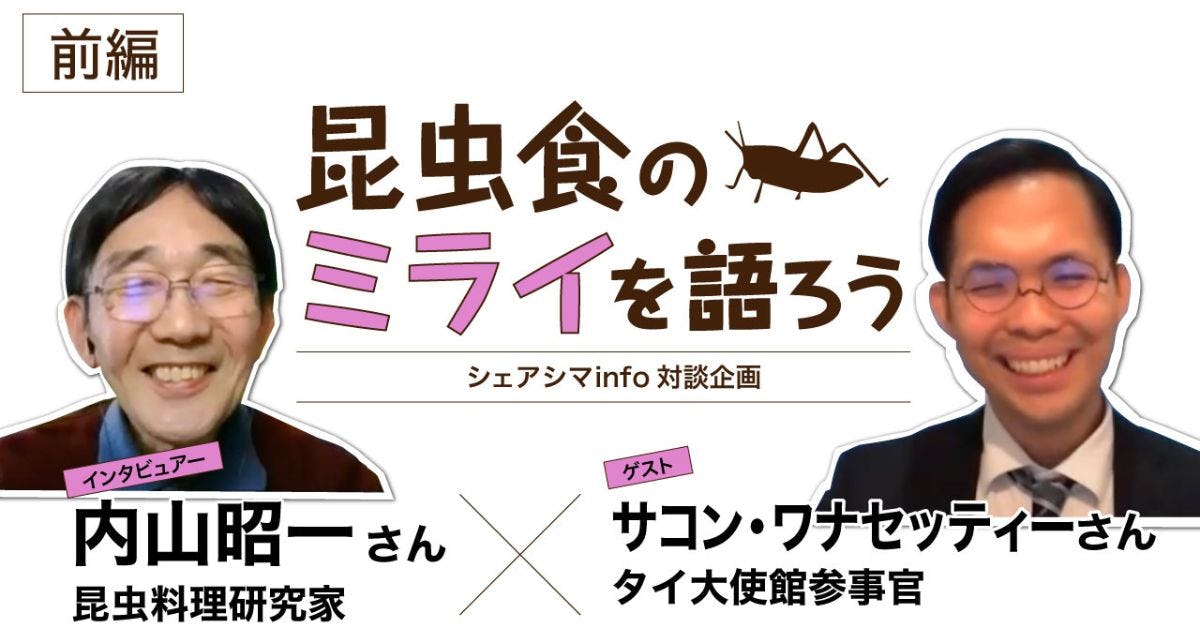
昆虫食のミライを語ろうvol.2前編【ゲスト:サコン・ワナセッティーさん(タイ王国大使館農務担当官事務所参事官(農務担当))】
昆虫食は「奇食」「物好き」「一部地域の食文化」として特殊性をもって語られてきました。それが2013年、FAO(国際連合食糧農業機関)の報告を機に、昆虫は急増する世界人口を支える「タンパク源=食料」としてみなされるようになり、もっとカジュアルかつポジティブに「昆虫を食べよう」という流れが日本でも一気に広がっています。 「かつて宇宙食といえば誰もが錠剤を想像していたが、今や宇宙ステーションでもおいしい食事ができるというイメージが定着した」と話すのは、昆虫料理研究家の内山昭一さん。昆虫食も「グロテスク」「おいしくない」という印象を脱却し、もっと身近に感じてもらいたいーー。そんな流れをつくっていくために、個性豊かなゲストを迎えて「昆虫食のミライ」を語ります。
【自己紹介】
内山)4、5年ほど前に昆虫食普及ネットワークを立ち上げたのを機に、昆虫食について一生懸命やっている内山昭一です。それまでは昆虫料理研究会という名前の任意団体で、20年以上虫を食べ続けてきました。比較的昆虫食が盛んな長野市に生まれたことがベースになっていると感じています。今回は、昆虫王国と言われているタイの方とお話しできるのをとても楽しみにしております。
サコン)タイ大使館農務担当官事務所のサコン・ワナセッティーと申します。タイ大使館にはいろいろな部局がありまして、僕のいる農務担当官事務所ではタイの農産物を日本の商社にPRするのが主なミッションです。昨年から昆虫食についてPRすべくいろいろなイベントなどを企画して実施してきました。タイというといろんなものを思いつくと思うんですけど、もしかしたら一部の方はタイといえば昆虫食を思い出すかもしれません。僕自身は実はタイの首都バンコク生まれで、完全なシティーボーイです(笑)。正直昆虫をたくさん食べて育ったというわけではないんですけれど、子供のころから昆虫食は身近でした。あちこちで売っていましたし、生活の一部だと感じているタイ人が多いと思います。
【サコンさんと昆虫食との関わり】
内山)サコンさんが小さい頃はバンコクでも屋台がいっぱいあって、昆虫が食べられる環境だったんですね。
サコン)そうですね。今ではバンコクも都市化が進んで結構屋台も減ってきたんですけども、僕が小さい頃はあちこちで屋台を見かけましたね。
内山)サコンさんが初めて食べた昆虫って何ですか?
サコン)6歳か7歳のころ親に連れられてタイ北部のチェンマイに行った時に、タケノコムシというのを初めて食べました。
内山)タケノコの中に入って育っていくタケツトガという蛾の幼虫ですね。日本でも非常に人気です。食べやすいので、昆虫食といってもこれならいけるという人もいます。サッと揚げて塩を振って食べると非常に食べやすい、おいしい昆虫だと思います。食べやすくおいしくて人気があるという点が、タイと日本ですごく共通していますね。
サコン)昆虫というと土のにおいがするというイメージを抱えている人が多いと思うんですけれども、タケノコムシは竹の中に住んでいるのですごくきれいで変なにおいもなく、食感もよかったです。
内山)竹の芯を食べているので、イメージとしてもすごくよくて、そこらへんが日本人にもうけているんじゃないかと思います。タイ語では「ロットドゥアン」と言いますか?
サコン)はいそうです。「特急列車」という意味です。
内山)なんで特急列車なんですか?
サコン)虫の外見が鉄道車両のように見えるんですよね。細長くて列車の形のイメージです。
内山)面白いですね。
【タイが「昆虫食王国」と言われているのは、なぜ?】
内山)農務関係のお仕事ということですが、昆虫以外で日本が輸入しているトップは何ですか?
サコン)タイの輸出額でいうと鶏肉が一番多いです。
内山)2番目がロットドゥアン?(笑)
サコン)そうだったらいいんですけれど(笑)、2番目は天然ゴムですね。
内山)ゴムですか、なるほど。最初にロットドゥアンを食べて、そのあとはどんな昆虫食歴ですか?
サコン)実は2番目に食べたところは日本の長野県なんですよ。大学が日本でしたので、長野県でハチノコを食べました。
内山)長野県は伊那の方ですか?
サコン)松本です。
内山)2度目を日本で食べたなんてすごいですね。本当に昆虫食の架け橋みたいですね。長野に行った理由は虫を食べに行ったんですか?
サコン)そうではなく普通に観光でした。知り合いにせっかくだから長野の食べ物を食べさせてほしいって言ったら、レストランで最初にハチノコが出されて、食べました。
内山)それは非常にいい出会いでしたね。よくタイは昆虫食王国といわれますが、どんな経緯があるんでしょうか?
サコン)タイには昆虫を食べる習慣、食文化があります。タイは農産物も豊富なんですが、なんで昆虫を食べる必要があるかというと、おそらく単においしいからだと思うんですよ。他の国の方と比べて、比較的早いうちから昆虫食のおいしさが分かっていたわけです。食材として、あるいはむしろ調味料として昆虫を使う習慣があったので、国の政策として産業化、近代化が進められました。
内山)なるほど。調味料、味付けという意味では、タガメなんていうのはタイではよく使われる食材なんですよね。
サコン)タガメのふりかけはすごく有名で、好評です。すごく風味がいいです。
内山)日本でタガメがおいしいですよっていうと絶滅危惧種だから取っちゃいけないんだって言われるんですが、日本のタガメじゃなくて台湾タガメ、ちょっと大ぶりのタガメのことですね。タイでは養殖まではしていないんですかね?
サコン)一般的に手に入りますので、おそらく。
内山)とにかくたくさんいるんですね。昔から食べられていたっていうことですもんね。
サコン)食材、調味料という意味では酸味としてアリの卵は昔も今もよく使います。アリは酸っぱいんです。
内山)アリが取れるのは乾季ですよね。タガメは年中取れるんですか?
サコン)タガメはほとんど年中取れます。アリの卵の時期は決まっていて、僕が聞いた話では高値で取引されてるそうで、かなり高い食材になっているようです。
内山)タガメはオスのフェロモンが風味につながるんですよね。オスの方が値段が高いと聞きますが、オスとメスでは結構値段は違うものですか?
サコン)違いますね。
内山)オスの場合はそのにおいがいろんな調味料、それこそふりかけにも使われますが、メスは普通どういう風に食べるんですか?
サコン)タガメといえば、つぶしてご飯と一緒に食べるイメージしかないんですよね。
内山)メスは小ぶりだし、お腹に卵が入っていることもあるので、素揚げか何かにしてバリバリと食べる印象を持っています。
サコン)ついこの間、タガメサイダーを飲みました。これは絶対試してもらいたいです。もう、爽やかですごくおいしいです。
内山)タイは非常に気候が暖かく虫も育ちやすいことから養殖がしやすく、これがタイを昆虫食王国にした大きな要因だと思います。日本の場合はやっぱり冬があるので、やはりタイの方が昆虫の養殖に向いていますよね。
サコン)まさにそうですね。放っておいても育つという環境が大きなきっかけだったと思います。今のコオロギパウダーを作るためのコオロギは、ちゃんとした設備で作ってると思いますが、昔は恐らく気候が合っていてたくさん獲れることが始まりだったのでしょう。今でも昆虫はたくさん獲れますし、かつ近代的な設備もできてあちこちで養殖をやってます。
【タイ東北部で盛んな昆虫食】
内山)タイといっても地域が分かれていますよね。東北部は今でも昆虫食が非常に盛んだと聞きますし、北部、中央部、東部、南部と分かれていますが、南の方はそれほど盛んではなく、やはり北部、東北部が盛んですか?
サコン)もともと昆虫を食べる習慣、食文化があるのはまさに東北部の方ですね。アリの卵などもよく使っています。名産地は中央部と東北部にあります。米農家の閑散期の副業として成長した昆虫食産業があって、食文化もあって、という感じですね。
内山)北部っていうのはまた少し違うんですね。
サコン)食べてるものが違うというイメージなんですよね。北部は僕が食べたタケノコムシのイメージなんですよ。屋台で販売しているものはだいたい東北の方がバンコクに出稼ぎに来ていて、生まれ故郷のふるさとの味を屋台で、というものなのです。北部でも昆虫を食べることはあるんですけども、やはり東北の方が昆虫食が盛んなイメージがありますね。
内山)やっぱり一番盛んなのは東北部なんですね。僕も昨年1月にタイに行って、最初にバンコクに行ったんですけど、昆虫食と接する機会がほとんどなくて。で、東北部のチェンマイとかイサーンに行くと、朝市とか屋台でバッタとかオケラとかゲンゴロウ、タケノコムシも売られていたんですよね。国の中でも地域によって違うんだなってすごく実感しました。さっきおっしゃったように、バンコクに来ている東北の方が故郷の懐かしい昆虫食に親しむ市場がバンコクにあるというのは、日本でいうと長野県人が東京に出てきてイナゴのつくだ煮やハチノコを食べたいなっていう時にそういうお店に行って食べるのと同じイメージですかね。昆虫食を見ると昔食べたなっていうイメージがあって、そこで食べてみようかとつながっていくのは日本でも共通していると思います。タイの現状ですけれども、昔ながらの自然採集で食べることにプラスして、コオロギの養殖は世界で一番盛んなんじゃないかと思うんですよね。コオロギの養殖場はやっぱり東北部が一番多いんですか?
サコン)もともとは食文化の影響もあって東北部で養殖が盛んでしたが、最近では設備も入ってきてどこでも育つようになっています。バンコクの郊外にもたくさん養殖場はあるんですよ。そして都市近郊の方が輸出につながりやすいんですよね。やはり東北部からだと距離もありますので、輸出を念頭に置く業者さんであればおそらくバンコク近郊に最新設備の密閉空間で管理する施設を作って養殖することが多いと思います。
内山)流通経路がしっかり発達しているバンコク周辺にそういったコオロギ養殖場がどんどん増えてきているわけですね。管理や安全性がしっかりしているところじゃないとなかなか輸出ができないということなので、そういった工場では例えばHACCPとかGAPとかいう基準にのっとって養殖されているということなんでしょうか?
サコン)まさにこれがタイの農業省が一番力を入れているところです。我々はキューマークと呼んでいるんですが、GAPをちゃんと取得している工場の製品であればキューマークをつけることができるんです。やはり海外に輸出するということを考えると、基準、認証をしっかりした方がいいとタイの農業省も思っていますので、結構早い段階から食用コオロギのためのGAPを制定しました。タイ農業省によれば世界初だということで誇りに思っています。
※GAP: Good Agricultural Practice(ギャップ) :食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組
※HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point (ハサップ):食品の原料から出荷までの各工程で可能性のある危害要因(異物混入や微生物の汚染や増殖など)を特定し管理する取組
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。






