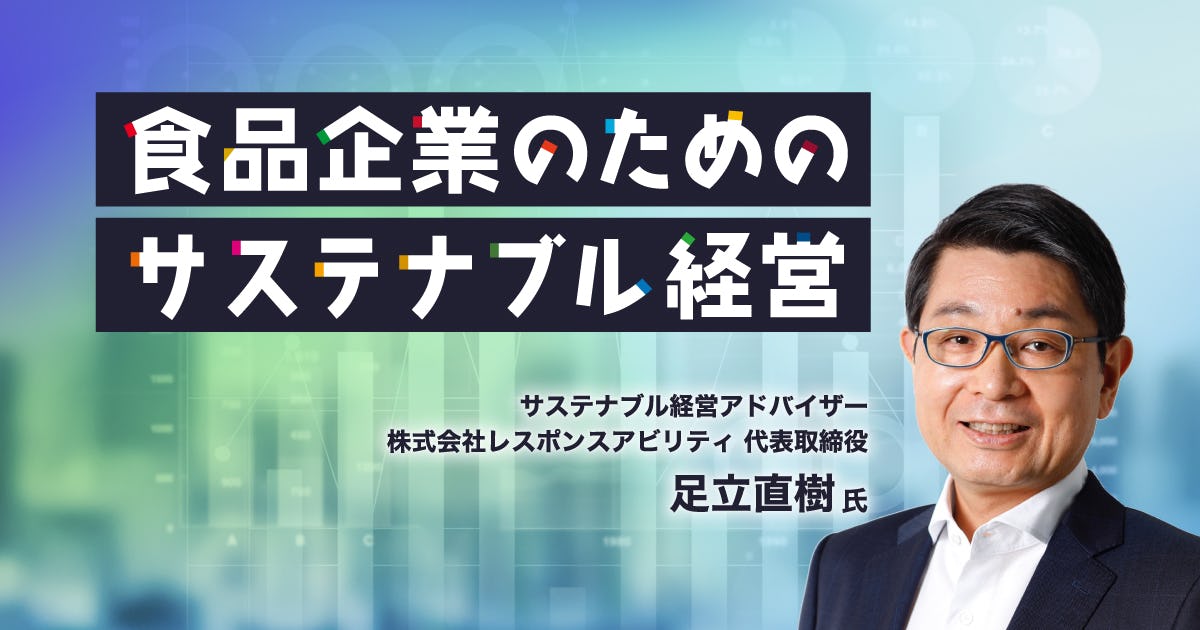
協働こそが、食品会社の未来をひらく鍵【食品企業のためのサステナブル経営(第30回)】
前回の記事を読む:海外市場の“いま”が示す次の一手 高付加価値の作り方【食品企業のためのサステナブル経営(第29回)】
7月に行われた参議院選挙で、少し気になる動きがありました。排外主義的な言説を掲げる政党が、特に若者層を中心に得票を伸ばしたことです。「日本人のための政治を取り戻す」といったスローガンは、経済の停滞や将来の不安の中で、心に響く人も少なくないのでしょう。私も日本は大好きですし、日本らしさや、日本の文化、そしてそれを支えて来た地域コミュニティをもう一度元気にしたいと願い、日々仕事をしています。
しかし、それと排外的になるのはまったく別です。特に食に関わる私たちは、この流れに対して冷静に立ち止まり、現実を直視する必要があります。なぜなら、食品産業は、すでに深く海外に依存し、そして多様性の中にこそ未来が見出せる産業だからです。
日本の食は、すでに「協働」で成り立っている
 足立直樹
足立直樹
サステナブル経営アドバイザー。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役。東京大学理学部卒業、同大学院修了、博士(理学)。植物生態学の研究者としてマレーシアの熱帯林で研究をし、帰国後、国立環境研究所を辞して独立。その後は、企業と生物多様性およびサステナブル調達の日本の第一人者として、日本の食品会社、飲料会社、流通会社、総合商社等の調達を持続可能にするプロジェクトに数多く参画されています。2018年に拠点を東京から京都に移し、地域企業の価値創造や海外発信の支援にも力を入れていて、環境省を筆頭に、農水省、消費者庁等の委員を数多く歴任されています。




