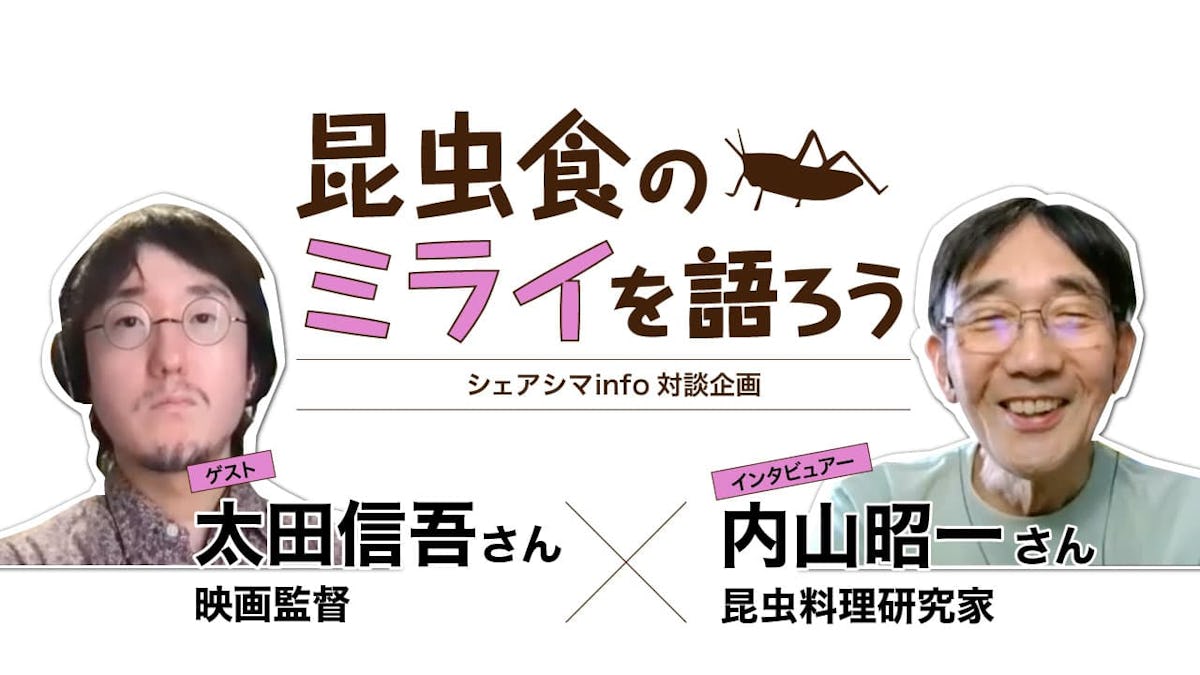
昆虫食のミライを語ろうvol.1【ゲスト:太田信吾さん(映画監督)】
昆虫食は「奇食」「物好き」「一部地域の食文化」として特殊性をもって語られてきました。それが2013年、FAO(国際連合食糧農業機関)の報告を機に、昆虫は急増する世界人口を支える「タンパク源=食料」としてみなされるようになり、もっとカジュアルかつポジティブに「昆虫を食べよう」という流れが日本でも一気に広がっています。
「かつて宇宙食といえば誰もが錠剤を想像していたが、今や宇宙ステーションでもおいしい食事ができるというイメージが定着した」と話すのは、昆虫料理研究家の内山昭一さん。昆虫食も「グロテスク」「おいしくない」という印象を脱却し、もっと身近に感じてもらいたいーー。そんな流れをつくっていくために、個性豊かなゲストを迎えて「昆虫食のミライ」を語ります。

自己紹介
内山)内山昭一です。毎日ではないんですが、結構頻繁に虫を食べながら暮らしています。季節的に今はセミが一番おいしい季節です。ミンミンゼミやアブラゼミなど、いろんなセミによって味が違います。そのほかにも最近はタケオオツクツクというかなり大きめな外来種のツクツクボウシが竹林で見つかることもあり、そんな新しい昆虫の食材を出会うことの楽しさに取りつかれてしまった</span><span style="font-weight: 400;">20</span><span style="font-weight: 400;">年です。昆虫食ってこんなにおいしくて環境的にもいいので、できるだけ大勢の方においしさや良さを知ってもらいたく、昆虫食普及ネットワークというNPO法人を5、6年前に立ち上げました。
太田)太田信吾です。映画の監督をはじめ、テレビ番組などの映像のディレクターをしています。2017年にNHKのドキュメンタリーで東南アジアの昆虫食を巡る旅を番組化したのが昆虫食との出会いです。このとき東南アジアの昆虫食を食べたことをきっかけとして、今に至るまですごく新しい食の魅力に引き込まれています。出身が長野県千曲市なので、振り返ると小さい時にイナゴを取った記憶がありまして「どこか昆虫の味って懐かしいな」という昔の記憶が食を通じて蘇ってくることもあります。
昆虫食との出会い
内山)東南アジアでNHKの番組って、どのような番組でしたか。
太田)「旅旅しつれいします」という、世界各地を旅する旅人たちがどんなテーマを持って旅しているかを紹介する番組です。リサーチをしている段階で、昆虫食をテーマにしている佐藤裕一さんという旅人に出会いまして、なんだこれは!?と思って出ていただきました。タイの東北部、イサーン地方のコーンケンでしたね。
内山)あの辺りは今でも昆虫食が結構残っていますね。
太田)コーンケン大学のユパ教授という昆虫食を専門とされている先生を訪問して、いろいろとタイの昆虫食事情を教えていただきながら、バンコクとコーンケンを中心にいろいろな昆虫食を食べました。番組ではコーンケンのコオロギ養殖農家さんを訪ねるところをドキュメントにしました。佐藤さんはすごい活発な方で、昆虫エネルギー研究所というNPOを主宰されています。
内山)まさに昆虫エネルギーを一身に吸収した人ですよね。すごい頑張っていらっしゃる。太田さんは長野県出身ですが、昔から昆虫食に対してはある程度興味があったんですか。
太田)そうですね。小さい時にイナゴの佃煮が実家で出たなとか、そういう記憶もあってあまり抵抗もなかったんですが、東京に出てきてからはあまり食べる機会がなくなっていて、その番組を機にまた思い出したという感じです。

★原料商品の掲載を希望される企業様は、会員登録(無料)で10品まで掲載可能です。
映像作品『エディブルリバー』について
内山)本格的に昆虫食を掘り下げてみようと思ったのは、佐藤さんと出会ったその番組以降ということですか。
太田)はい。2020年、コロナでロックダウンの期間中に、実家のある長野県千曲市に半年ほど戻りました。映像の仕事も一時延期になり時間があって、長野県中を一人で旅した時にザザムシとか蜂の子とかいろいろな昆虫食を食べさせてもらえまして。
始まりはザザムシ漁の漁師さんでした。中村さんと今年引退された菅沼さんという漁師さんがいらっしゃるんですけど。まず漁師の高齢化が課題だと知り、そこからどうやってその食文化が今後継承されていくのかと。ザザムシも食べたらすごくおいしかった。
内山)ザザムシは確かにすごくおいしいし良いんですけど。非常に(漁師は)高齢化してきているし、川が護岸工事されて漁が非常に難しくなってきているというのが現状です。そうした中であの上伊那農業高校の高校生はすごいですね。情熱がものすごい。
太田)去年(2021年)半年ほどかけて、上伊那農業高校の皆さんがザザムシを食べやすくふりかけにする取り組みをドキュメンタリー化しました。大月さんという主人公の女子高生は駒ヶ根出身で小さい時から給食でザザムシが出ていたそうで、ザザムシを食べるということが身近な体験としてベースにあったのだろうなと取材していて感じました。
この高校には、食を切り口に生徒の皆さんが自発的にいろいろなプロジェクトを立ち上げて運営するグローカルコース(グローバルとローカルをかけたユニークなコース)があります。例えばこうじを利用した甘酒など、地域の食品や食文化を扱っていろいろな商品開発をしようという取り組みをしていて、その一つがザザムシでした。
内山)給食というのはかなり大きなインパクトがあると思うんです。ただ、今ではなかなか給食で虫が出る学校ってそんなにはありません。いろんな人の意見を聞くと、小さい頃から経験した方がいいので、一番手っ取り早いのがまず給食だろうと。給食に出れば子供の頃から昆虫食に慣れてくるので、大人になっても継続していくんじゃないか、食品として捉えることができるんじゃないかという意見がかなり多いんですが、今では給食の安全面などから導入がかなり厳しくなってきていて、給食で虫を出すのは難しいようです。
この映画を見ると、伊那谷だけの文化っていうのを強調されていて、そういう局地的な文化って今もう消滅しそうなんですけど、ザザムシを養殖することまで考えている。これからの昆虫食に期待できる一つの方向性があるんじゃないかなと思いまして、この映画が非常に参考になりました。
新作『イナゴンピック』の撮影背景
内山)イナゴンピックの映像を撮られて、どうでしたか。
太田)僕も昆虫食の魅力に取りつかれてしまったところがあって、どうやったら広げていけるかなっていう思いはずっと持ってます。環境にいいからという切り口では自分でもそんなに食べたいなとは思えないので、やっぱり娯楽性とかおいしさを切り口にしないといけないなと。楽しくておいしいってところにまず出会いたいなというところで、ザザムシのふりかけと出会いました。イナゴンピックに関しては、オリンピックとイナゴンピックをかけて、イナゴ取りをゲーム、行事としてみんなで楽しく捕ろうっていうイベントの趣旨がすごく良い。親子の交流の時間でもあり、都会の子どもたちがなかなか経験できない田んぼで自然とふれあう時間でもあり、そのエンターテインメント性にすごく引かれました。
内山)僕も同感です。これは群馬県の中之条町が始めて、もう10年以上やってると思うんですけど、前に一度参加しました。すごくみんな楽しそうにやってるんですよ。親子でとても仲が良くて、親子のつながりや触れ合い、話もたくさんできてすごく面白いんだけど、なかなか東京じゃ難しいかなと思っていたら、たまたま家の近くに田んぼがあって、そこでやれちゃった。イナゴがいないとできないわけですから、本当に幸運でした。東京でできたことは本当に良かったなと思います。
映画の中にもありましたが、毎年優勝する男の子、シュン君に「捕まえるコツは?」って聞いた時に、彼は「感じること」だと答えていたんですよね。確かにそうだなと思って、すごく印象に残りました。やっぱり五感をフルに活用して捕まえることが狩猟の原点だけれど、そういう五感というものが全然使われない環境になっている中、人間が本来持っている動物的な勘をもう一度自分で感じ直していく機会があることはすごく良い。しかも子どもの頃のこの経験が強く印象に残って大人まで継続していくとしたら、イナゴンピックはすごく意義があるんじゃないかなって。有機の田んぼっていろんな生き物があふれてるじゃないですか。世界にはこんなにも生き物があふれているということを実感する楽しさ、それから捕って食べるという命をいただくような実感。そういう喜びが、あのコンパクトな映像の中にきっちり詰まっていて、昆虫食にとっては最高のドキュメンタリーじゃないかなと思っています。
映像作品として伝えたいこと
内山)太田さんにとって、昆虫食を映画にする意味とは何ですか。
太田)一つは食の新しい可能性です。小さな時から慣れた食事が当たり前の食事という風に思ってしまっていますけれど、まだまだ世界を見渡すといろんな食文化があって、さまざまな感覚の体験、食の多様性、可能性、そういったものが秘められています。旅する中で食べたことがないいろんなものを食べることが好きなので、そういう新たな体験としての可能性を伝えていきたい。また昆虫食文化を知ることで、地球環境の持続可能性も再認識できればいいのかなって思いますね。入り口はやっぱり美味しかったり楽しかったりというところを軸に伝えていきたいです。

 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。






