
食品原料だからこそ!アニメーション動画を使う新PR戦略【タイショーテクノス】
株式会社タイショーテクノス(東京都港区)は、主に食品添加物の製造・販売を行っており、加工食品や調味料などに使用される保存料、品質改良剤、着色料、寒天・ゲル化剤などを提供しています。扱う製品の特徴や使用方法が特殊なため、顧客への理解を促すことに課題を抱えていたとのこと。そんな同社が、シェアシマのアニメーション動画制作を活用するまでの経緯や、それによって得られた効果、今後のシェアシマに期待することなどを聞きました。
話を聞いた相手
.png)
- 製品の特徴や使用方法を分かりやすく伝える事に苦労していた
- 広告予算に限りがあるため、より効果的なPR方法を模索していた
- 現状の広告手段だけでは、自社の商品説明が顧客に伝わりきらないと考えていた
- 動画の活用で、製品の特徴を視覚的にわかりやすく伝えられた
- シェアシマ商品開発セミナーの活用で、新規顧客の開拓が容易になった
- 動画+セミナーの相乗効果で、効率的なPRが実現できた
食品添加物市場を牽引する、タイショーテクノスの歩みと挑戦
タイショーテクノスは、1959年に設立された日本の食品関連企業で、食品添加物の製造・販売を主な事業としています。「豊かで潤いのある食文化と快適な生活環境の実現に貢献します」という企業理念の下、食品製造に必要不可欠な製品を提供することで顧客のニーズに応えています。
同社の製品は、食品添加物(保存料、日持向上剤、品質改良剤、着色料、香料、寒天・ゲル化剤)や、健康食品素材(D-リボース、GABA、植物性乳酸菌K-1,K-2、サラシアなど)をはじめ、工業用薬剤の製造・販売と幅広く事業展開しています。
食品添加物は、加工食品や調味料など多岐にわたる食品に利用されており、食品の品質向上や安全性確保に寄与しています。一方で、製品は見た目が粉末状であることが多いため、ひと目では効果・効能がわかりづらいといいます。そのため、製品の特徴を顧客に理解いただくことに課題を感じていたそうです。
従来は、専門誌の広告枠を活用することで製品PRに努めていたものの、どうしても文字や一枚絵のみの表現に難しさを感じていました。
「白い粉の正体」を伝える!アニメーション動画で食品添加物をPR
阿久根さんにとって、動画制作を考えるきっかけとなる、ある出来事がありました。それは、小学生の娘さんの授業参観でのこと。授業中の一幕で
「『お父さんは何のお仕事してるの?』という質問に対して、娘が『白いお粉を売っている!』と答えたんですよ。いやいや怪しい商売じゃないんだと」
その時、「どうにかして分かりやすく説明できないだろうか?」と改めて感じ、阿久根さんは動画の制作を視野に入れました。
娘さんとのエピソードを笑いながら話す阿久根さん(中央)
車一台のコストに見合う価値:シェアシマの動画が示す可能性
しかし、いざ動画制作するにしても、次に立ちはだかったのが、費用の問題でした。
大手広告代理店に一から制作を依頼すると、車一台を購入できてしまうほど費用がかかる場合もあります。それほどの予算を広告費に当てるのは容易ではなく、頭を悩ませていたといいます。
「シェアシマの動画を活用した理由は、他の広告代理店などと比較して圧倒的にお手頃価格であったことです。それに、キャッチーな言葉とともにわかりやすいビジュアルで製品の魅力を表現してくれます。どうしても説明が長くなってしまう部分も 『要するに、こうゆうことですよね』と、端的にまとめてくださるので助かっています」(阿久根さん)
株式会社タイショーテクノス「会社案内」動画(同社公式YouTubeより)
営業・展示会・社内でも!タイショーテクノスの動画活用例
実際にはどのような場面で動画をご活用されているのでしょうか。さらに詳しく、話をうかがいました。
「営業先でのプレゼンや展示会、それに学会等の広告の場面でも活用しています。以前は、カタログや試食見本などを営業先に持っていって説明するのが主流でした。しかしながら、例えば色調やゲルの揺れる様子などは、口頭や数値で説明するよりも見た方が早いというものがあります。それらをきれいに分かりやすく、1つの動画にまとめていただいています」(阿久根さん)
しかも、顧客が遠方にいてすぐにおうかがいができない場合にも、あらかじめ動画を送付するだけでざっくりと製品説明ができるため助かっているそうです。メールや電話だけのコミュニケーションよりも、顧客の製品理解が格段に上がるためです。
そして特に、アニメーション動画が活躍したのが、展示会の会場でした。
動画を大画面のモニターで再生しておくことで、立ち止まって動画を見てくださるお客様が増えたそうです。かつては、多くの方がブースの前を通りかかるものの、一人一人にもれなく声掛けができずに見込み顧客を取り逃していた可能性もありました。
「実は以前、『BtoBの食品添加物メーカーで動画まで作るのはめずらしいですね』 と業界紙の方から言われたことがあります。それがきっかけで、記事にまで取り上げていただいたんですよ。今では、業界紙の方だけでなく幅広いステークホルダーに対して、動画を活用しています」(玉村さん)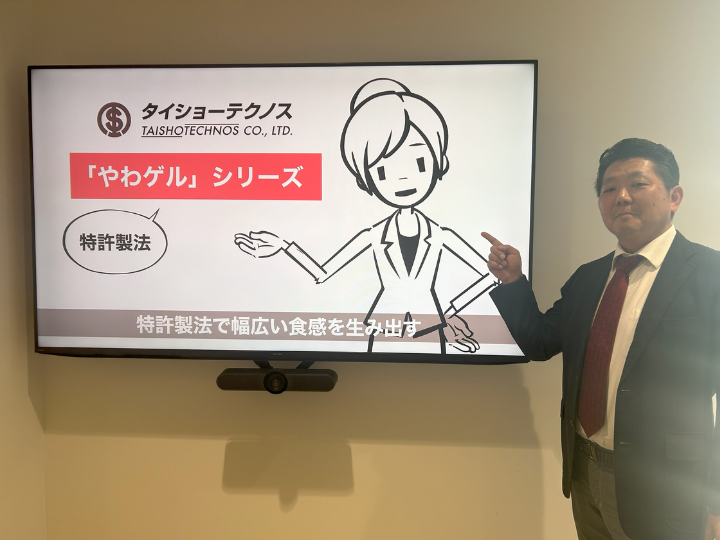
動画を使って「やわゲルⓇ」シリーズの説明をする阿久根さん
さらに話をうかがうと、動画が社員教育の一翼も担っているというのです。
同社は扱う事業領域の広さから、社員であってもすべての商品を事細かく理解することに一定の時間を要するといいます。しかしながら、自社商品が最終的にどう展開されているかを知るのは、モチベーション維持の観点でも重要です。そのため同社では、社員が利用するイントラネット上で動画を展開し、製品理解を促しています。
なお、動画は同社ホームページ内にリンクされているほか、公式Youtubeチャンネルにも掲載されています。そのため、社外の方であっても閲覧できるようになっています。過去には、動画を見て新卒採用に応募してきた学生もいたということです。
1分動画で差をつける!セミナー成功のための新スタイル
ここで、同社が実践している「動画×オンラインセミナー」の活用事例を紹介します。
同社は、シェアシマ商品開発セミナーにも何度もご登壇いただいており、初回は第6回の商品開発セミナーでした。当時、ウェビナーに出演すること自体が初めてだったそうですが、「まずは試しにやってみよう!」という軽やかな感覚で登壇を決めたそうです。
「それ以来、定期的に登壇していますが、実は業界誌に一回広告掲載するのとシェアシマ商品開発セミナーへの登壇料がだいたい同じ金額なんですよ。それならば、広告掲載を一回見送って、シェアシマセミナーに登壇してみようと思ったわけです」(阿久根さん)
また最近では、シェアシマで制作したアニメーション動画をセミナー冒頭で流していらっしゃいます。それにも、はっきりとした意図がありました。
「冒頭に動画を流すことによって、聴講者の皆さまに商品理解を深めていただける効果があります。セミナー枠は20分ですが、その枠内でいかに効率的に商品理解を深めていただくかが重要です。動画はたった1分で会社概要とおおまかな商品説明をしてくれるので、最適な営業ツールです。セミナー登壇が決まったら、登壇日から逆算して新たな動画制作を依頼しています」(阿久根さん)
シェアシマの動画は、プロのコンサルタントによる1時間程度のヒアリングをもとに、台本制作~校正などを経て1ヶ月程度で制作されます。プレゼンテーション資料の作成は個人のスキルが反映されやすいうえに、それなりの時間を要します。万が一、プレゼンテーションが上手くできないと、肝心の製品の魅力が顧客に伝わらなくなってしまいます。しかしながら、動画は一度作ってしまえば誰が説明してもある程度はクオリティを担保できるため、効果的な製品PRが可能です。
シェアシマセミナーの聴講者アンケートによると、同社の発表内容に対して毎回8割以上の方が好感を示しているほか、毎回数名から資料請求の要望が届くといいます。
写真:動画を有効活用した同社のシェアシマ商品開発セミナー登壇の様子
食品業界におけるデジタルPRの新潮流
「動画×オンラインセミナー」の活用は、新たな見込み顧客へのアプローチにもつながっているそうです。同社では食品添加物を扱うことから、商品開発の初期フェーズになかなか加われないことに課題を感じていました。そのため、月一回は顧客先を訪問し、地道に関係を築き上げていたといいます。
さらにコロナ禍が相まって、対面での商談が難しい時期が続きました。そこで考えたのが、「Web上で広くリーチすることで、新たな顧客を得ること」。「動画×オンラインセミナー」は、新しい見込み顧客を獲得するアプローチとしても上手くフィットしました。
ちなみに、シェアシマ事務局にはこんな声も届いています。同社の登壇内容を視聴していた別の企業から、「タイショーテクノスさんと同じ方法で、自社商品のPRをしたい」といったものです。動画やオンラインセミナーの活用は今や各業界で市民権を得ていますが、食品業界においてもその波が広がりつつあります。
今後は、既存顧客はもちろん、他業界を含めた新たなコラボレーションも検討しているそうで、時流に合った新製品の開発を視野に入れているそうです。
シェアシマが育む企業間ネットワーク、未来への期待
最後に、玉村さんがシェアシマに対してこんな期待を寄せてくださいました。
「実は、セミナー後に登壇企業同士のコミュニケーションが生まれているんです。『御社のその商品いいですね』とか『今度そのサンプル取り寄せたいです』など。シェアシマ商品開発セミナーは毎回テーマが設定されているため、関連商品を扱う企業が集まります。その関係で、純粋に他社さんの商品は気になるんですよ。いずれシェアシマさんの方で、登壇企業を束ねた交流会などを企画してくれると、横のつながりがもっと育まれるかなと期待しています」(玉村さん)
シェアシマというサービス名は「その原料シェアしませんか?」から来ています。食品原料のシェアはさることながら、今後は「情報」「人脈」などあらゆる資源を”シェア”するプラットフォームにしていきたいと、身が引き締まる思いでインタビューを終えました。
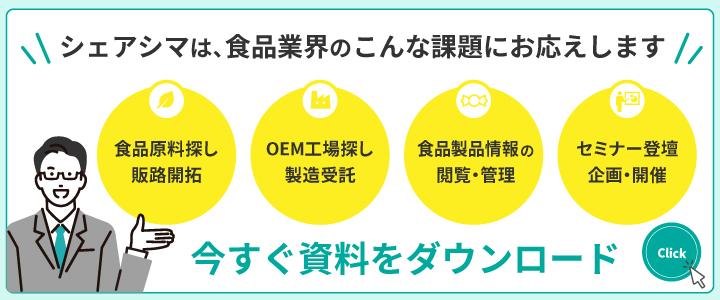
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。




.jpg?fmg=webp&q=50&w=300&fit=max)

