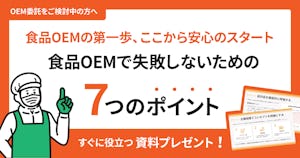急伸する「フードテック」を知ろう(前編)~社会問題の解決を目指すフードテック~
フードテックとは
「フードテック」という言葉を聞いたことがありますか?
フードテックは食×テクノロジー(技術)を意味し、食品関連分野にサイエンスやITを導入することにより更なる食の可能性を探る動きを指します。生きていく上での根幹ともいえる「食」は農業漁業から、食品製造、流通・保存、調理、配送など様々な分野にまたがります。関連したお仕事をしている方も多いでしょうし、末端の消費者として考えれば、フードテックによる新サービスや新ビジネスはまさに私たち一人ひとりの生活に直結しているわけです。
とはいっても、「フードテック」という言葉だけでは具体的なイメージは湧きにくいかもしれませんね。まずは社会問題の解決という視点から、フードテックを探ります。
食糧問題の解決を目指すフードテック
フードテックの目指す一つの行き先は食品ロスや将来のたんぱく源不足の解消といった食糧問題の解決です。食品ロスの問題は大変深刻です。国連食糧農業機関(FAO)によれば、食糧廃棄量は世界中では年間約13トン。これは人の消費のために生産された食料のおよそ1/3にも上るといいます。
ITを活用することで需要と供給をより精緻に予測することができれば、家庭に届く前までの食品ロスが減少すると考えられます。家庭に届いたあと、さらに最新技術により品質を保持できる保存期間が延長され、誰でも簡単においしく調理できる自動調理などが実現すれば、家庭内での食品ロスも減っていくでしょう。食品パッケージが変わってくれば、プラスチックごみの減少へもつながるでしょうし、流通のロスが少なくなればその分の輸送量が減り、排出CO2も削減できるなど、影響は計り知れません。たんぱく源不足も大きな食糧問題ですが、代替肉や培養肉の分野が解決の糸口となる可能性を秘めています。さらにはたんぱく源不足だけではなく、貧困層の栄養不良による健康問題、それとは逆の富裕層の食べすぎによる健康被害といった問題に対応できる代替肉や培養肉は、今後ますます注目されていくことでしょう。
人手不足をテクノロジーが解決する?
日本の人口は10年連続で減少し続けています。少子高齢化の流れは今後も加速の一途をたどりそうです。この労働力人口の減少をテクノロジーによって解決できるのでしょうか。
実は、その可能性は十分にあります。ドローンを活用した農薬散布、AIによる自動灌漑、食品工場でのロボット化などはすでに実現していますし、畑ではなく工場で野菜を生産することも今後ますます増えていくでしょう。さらには小売り・飲食業界でも調理や接客をロボットが行うことも当たり前の時代がやってくるかもしれません。あるいは小売という業態が変化していく可能性もあります。一昔前は、どのようなものでも出かけて行って店舗で買うのが一般的でしたが、現在の通信販売の躍進は皆さんご存じのところです。今後この流れがますます加速し、もしかしたら普段食べる生鮮食品についてもオンラインで購入し届けてもらう形が普及していくのかもしれません。
近い将来の購買形態がどうなるかは未知数ですが、フードテックがさまざまな可能性に満ちていることは確かです。
今回の記事のまとめ
以上のように、フードテックは社会問題の解決を目指して急伸してきています。しかしそれだけではフードテック全体をとらえたとは言えません。もう一つ別のアプローチとして、フードテックは食の多様化を目指しています。次回後編ではこの食の多様化、パーソナライズ化されたニーズを満たすフードテックについてお伝えします。
後編はこちら
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。