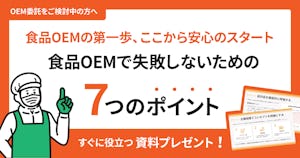味を数値化する「味覚センサー」とは
最近どんな美味しいものを食べましたか。その味わいを思い出すことができますか。
人間が感じる味は5種類、塩味・酸味・甘味・うま味・苦味の五味と言われます。複雑な味を言葉で細かく表現することは難しいですが、「おいしい」という便利な言葉がありますね。この「おいしい」という味は非常に主観的であり、五味が複雑に絡み合って感じられるものなので、機械で計測し数値化するのは難しそうなイメージです。
しかし!味覚センサーはなんとこの「味わい」を一定の数値として表すことができるのです。今回はこの驚くべき味覚センサーについて探っていきます。
味覚を感じると体内で何が起こるのか
そもそも味を感じるとは非常に主観的な感覚のように思えますが、体内では何が起こっているのでしょうか。
食品の中に含まれる味のもととなる物質が舌にある味蕾(みらい)と触れるとわずかに電圧が発生します。この電位変化が脳に伝わることで甘い、苦いといった味覚が知覚されます。つまり情報が神経を伝って脳に届くという反応は電気的なものと言えるわけです。事実としてはそうなのですが、この体内でそんなことが起こってると思うと、少し不思議な気持ちになりますね。
味覚センサーの可能性
この味蕾(みらい)における電位変化を人工的な舌で再現し、それを測定することで味を数値化しようと開発されたのが、味覚センサーです。
1990頃にはすでに味認識についての共同研究が行われており、1993年には世界初の味覚センサーが実用化されました。その後コンピュータ技術の発展とともに飛躍的に改良が進み、研究機関のみならず世界中の企業等にも導入されています。現在では人工知能なども組み込まれ、複雑な味をより高い精度で数値として表現できるまでになっています。
プリンに醤油をかけるとウニの味がする、という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これも実は味覚センサーが導き出した味の足し算なのだそうです。味覚センサーにより味を数値化できれば、食品メーカーにとっては安定した味を目指すにあたって大きな支えになります。
また相性のいい味の組み合わせが分かるということから、メニュー開発やスーパーでのクロスマーチャンダイジングの面でも活用が期待されます。ただし、最終的な「おいしさ」とは味覚だけではなく、それ以外の嗅覚、視覚、触覚、聴覚まで含めた五感によってもたらされます。
おいしさとは「体験」である
しかしそれだけがおいしさをもたらす要素というわけではありません。
空腹は最高のスパイスだ、という言葉もあります。器や雰囲気、飲食を共にする相手やシチュエーション、ひいては本人の健康状態にも「おいしさ」が大きく左右されることは、皆さんご自身の体験からも納得できますよね。つまり、おいしさとは味にとどまらない、丸ごとひっくるめた一つの「体験」なのです。
味覚センサーは味覚の面から「おいしさ」を支えてくれます。これを土台に「体験」をより良いものにするためには、一人ひとりが味覚以外の要素にも気を配ることが大切だということも忘れないようにしたいものですね。