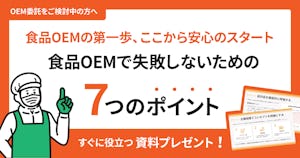承認業務の手間を「9割」削減、機械トラブルの復旧も迅速化【紀州高下水産の“カミナシ”活用法】
株式会社紀州高下水産(以下、紀州高下水産)は、小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に対応するため、カミナシを導入。「ただ記録しているだけ」だった衛生管理を脱却し、効率的かつ的確な管理体制を実現。これにより、大幅な業務効率化や生産機械に不備が発生した場合の早期復旧が可能になるなど、さまざまな導入効果が生まれています。同社のカミナシ活用法と効果についてご紹介します。
紙による非効率なアナログ作業をなくし、現場のDX化を推進するサービスです。手書き情報のデータ化から集計、報告など、これまで紙やエクセルで行っていた事務作業やルーティンワークをデジタル化し、モバイルアプリでの一元管理を可能にします。
カミナシ詳細はこちら

2021年6月のHACCP完全義務化に伴い、紀州高下水産でも小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められるようになりましたが、その体制をどのように作るかが課題でした。
以前同社では、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録や従業員の入室記録、機械の点検表などを紙の管理表やホワイトボードに記録していましたが、事実上「ただ記録しているだけ」の状態で、正確に管理できているかといえばかなり疑わしく、また記録や承認にも多大な時間を要していました。紙の管理表は事務所に溜まる一方で、承認後に見直すことはほぼありません。時折、取引先のバイヤーから問合せがあり、管理表を見直して作業記録について回答することがありますが、その作業に2日ほどかかるのが当たり前でした。
こうした状況のままHACCP対応を進めれば、作業記録は煩雑化し、従業員への業務負荷が大幅に高まると見込まれました。また、紙の管理帳票の印刷や設置、回収、チェック、保管といった一連の作業に要する手間も増大します。
そうした課題を解決するにあたり、カミナシの
・食品工場でよく利用されている
・作業記録から承認、データの蓄積・閲覧など、紙の管理表にまつわる作業を一気通貫して電子化できる
・フォーマットや画面のデザインがシンプルでわかりやすそう
という点に魅力を感じ、導入を決めました。

現在、紀州高下水産では冷蔵庫・冷凍庫の温度管理や従業員の入室記録など、HACCP対応に必要な衛生管理をカミナシで行っており、衛生管理は非常にスムーズになりました。以前は紙の管理表の承認には1日10分ほど要していましたが、現在では1分程度で完了できます。つまり、承認にかかっていた手間が約9割削減され、月間では9時間の業務効率化効果が生まれています。
特に、生産機械の不備に関する対応は大きく変わりました。以前は瞬間凍結機などの生産機械に不備が見つかった際には、従業員から管理者に連絡が届き、管理者から修理業者に連絡をして、生産機械を修理してもらうといった流れでした。これでは復旧に2日ほどかかってしまい、工場の生産力が落ちてしまいます。
しかし現在は、生産機械の不備をカミナシに記録すると、画面上に修理業者の連絡先が表示される設定をしているため、従業員が直接、復旧作業を依頼できます。加えて、タブレットで破損部分を撮影して共有できるため、離れた場所にいても不備の状況が把握可能です。同社ではカミナシを導入して以降、2回ほど不備が発生しましたが、いずれも半日程度で生産機械を復旧できています。
食品工場には、衛生管理の状況などを確認するため、取引先の顧客がしばしば視察に訪れます。そのときに、カミナシでの衛生管理を見せると非常に良い反応が返ってきます。やはり、取引先としても「過去の作業記録をすぐに確認できる」「経営者がほぼリアルタイムで現場の状況を把握できる」という環境は、信頼性が高いと感じるのではないでしょうか。

同社では平均40代から60代の従業員が勤務しており、タブレット操作に不慣れなメンバーからはカミナシ導入に戸惑いの声もあがっていました。しかし、実際に使っていくうちに徐々に抵抗感は薄れ、今ではむしろタブレットの方が使いやすいし衛生的だと評判です。
高下水産では主に衛生管理にカミナシを導入していますが、例えば生産数の管理や業務マニュアルの作成も可能なため、新人教育のコスト削減などにも活用できます。カミナシの適用範囲を広げることで工場内の完全ペーパーレス化ができ、より効率的な運用が可能になります。
導入は、現場を把握している工場長などを推進リーダーに据えて推進されるほうが、従業員の要望に沿ったシステムを構築できるのでおすすめです。

本社:和歌山県和歌山市、代表取締役:高下昭人
主にあじ、さば、さんま、のどぐろなどの干物を製造・販売する水産加工会社。従業員数は約10名で、1日に約3,000枚の干物を生産。紀州備長炭を用いた独自製法で作られた「こだわりの干物」は、たびたびメディアでも取り上げられている。
紀州高下水産
「カミナシ」とは
紙による非効率なアナログ作業をなくし、現場のDX化を推進するサービスです。手書き情報のデータ化から集計、報告など、これまで紙やエクセルで行っていた事務作業やルーティンワークをデジタル化し、モバイルアプリでの一元管理を可能にします。
カミナシ詳細はこちら
導入前の課題

2021年6月のHACCP完全義務化に伴い、紀州高下水産でも小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められるようになりましたが、その体制をどのように作るかが課題でした。
以前同社では、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録や従業員の入室記録、機械の点検表などを紙の管理表やホワイトボードに記録していましたが、事実上「ただ記録しているだけ」の状態で、正確に管理できているかといえばかなり疑わしく、また記録や承認にも多大な時間を要していました。紙の管理表は事務所に溜まる一方で、承認後に見直すことはほぼありません。時折、取引先のバイヤーから問合せがあり、管理表を見直して作業記録について回答することがありますが、その作業に2日ほどかかるのが当たり前でした。
こうした状況のままHACCP対応を進めれば、作業記録は煩雑化し、従業員への業務負荷が大幅に高まると見込まれました。また、紙の管理帳票の印刷や設置、回収、チェック、保管といった一連の作業に要する手間も増大します。
そうした課題を解決するにあたり、カミナシの
・食品工場でよく利用されている
・作業記録から承認、データの蓄積・閲覧など、紙の管理表にまつわる作業を一気通貫して電子化できる
・フォーマットや画面のデザインがシンプルでわかりやすそう
という点に魅力を感じ、導入を決めました。
導入の成果
HACCP対応を実現

現在、紀州高下水産では冷蔵庫・冷凍庫の温度管理や従業員の入室記録など、HACCP対応に必要な衛生管理をカミナシで行っており、衛生管理は非常にスムーズになりました。以前は紙の管理表の承認には1日10分ほど要していましたが、現在では1分程度で完了できます。つまり、承認にかかっていた手間が約9割削減され、月間では9時間の業務効率化効果が生まれています。
ほぼリアルタイムで現場の状況を把握できるように
特に、生産機械の不備に関する対応は大きく変わりました。以前は瞬間凍結機などの生産機械に不備が見つかった際には、従業員から管理者に連絡が届き、管理者から修理業者に連絡をして、生産機械を修理してもらうといった流れでした。これでは復旧に2日ほどかかってしまい、工場の生産力が落ちてしまいます。
しかし現在は、生産機械の不備をカミナシに記録すると、画面上に修理業者の連絡先が表示される設定をしているため、従業員が直接、復旧作業を依頼できます。加えて、タブレットで破損部分を撮影して共有できるため、離れた場所にいても不備の状況が把握可能です。同社ではカミナシを導入して以降、2回ほど不備が発生しましたが、いずれも半日程度で生産機械を復旧できています。
バイヤーなどの取引先からも高評価
食品工場には、衛生管理の状況などを確認するため、取引先の顧客がしばしば視察に訪れます。そのときに、カミナシでの衛生管理を見せると非常に良い反応が返ってきます。やはり、取引先としても「過去の作業記録をすぐに確認できる」「経営者がほぼリアルタイムで現場の状況を把握できる」という環境は、信頼性が高いと感じるのではないでしょうか。
従業員からも「使いやすい」との声

同社では平均40代から60代の従業員が勤務しており、タブレット操作に不慣れなメンバーからはカミナシ導入に戸惑いの声もあがっていました。しかし、実際に使っていくうちに徐々に抵抗感は薄れ、今ではむしろタブレットの方が使いやすいし衛生的だと評判です。
カミナシ活用のポイント
高下水産では主に衛生管理にカミナシを導入していますが、例えば生産数の管理や業務マニュアルの作成も可能なため、新人教育のコスト削減などにも活用できます。カミナシの適用範囲を広げることで工場内の完全ペーパーレス化ができ、より効率的な運用が可能になります。
導入は、現場を把握している工場長などを推進リーダーに据えて推進されるほうが、従業員の要望に沿ったシステムを構築できるのでおすすめです。
シェアシマinfo読者の皆様へ
カミナシ様より「食品業界におけるカミナシ活用事例集」をご用意いただきました。
ご興味のある方は、以下より無料で、ダウンロードいただけます。
>>> https://lp.kaminashi.jp/ebook/food_casestudy/ssinfo
ご興味のある方は、以下より無料で、ダウンロードいただけます。
>>> https://lp.kaminashi.jp/ebook/food_casestudy/ssinfo
株式会社「紀州高下水産」とは

本社:和歌山県和歌山市、代表取締役:高下昭人
主にあじ、さば、さんま、のどぐろなどの干物を製造・販売する水産加工会社。従業員数は約10名で、1日に約3,000枚の干物を生産。紀州備長炭を用いた独自製法で作られた「こだわりの干物」は、たびたびメディアでも取り上げられている。
紀州高下水産