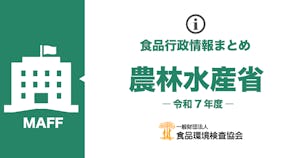食品の「無添加」表示に規制強化。煩雑化やコスト増の懸念も
2022年3月30日、消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。これにより、食品の包装などに「無添加」「不使用」と記載する際の規制が厳しくなります。今回の記事では、その背景と共に、ガイドラインの概要や現場での対応について紹介します。
分かりやすい表示を、添加物にガイドライン
消費者庁が今回のガイドラインを策定した理由として、「消費者の誤解を招くような表示の多さ」が挙げられます。これまで「無添加」「不使用」という表記について明確なルールはなく、食品メーカーの判断に委ねられていました。そのため、パッケージに「無添加」と書かれていても「具体的に何が不使用なのか分からない」という声もありました。食品を加工する際に添加物を使わない「無添加食品」の場合、原材料には添加物を使っていることもありました。
このような分かりづらい食品表示を改善するために、消費庁が発表したのが今回のガイドラインです。ガイドラインの策定にあたり2021年3月から計8回の検討会が開催され、消費者や事業者に対するヒアリングや、食品添加物の使用状況の調査が行われました。
パッケージ変更を求められる食品メーカー
ガイドラインでは、禁止事項に該当する可能性がある不使用表示を10個の類型に分けて示しています。その中には「何が無添加なのか分からない単なる『無添加』の表示」「健康や安全と関連付ける無添加や不使用の表示」が含まれています。
今回のガイドライン策定を受けて、食品メーカーなどではパッケージの変更が必要となり、製造コストや情報管理などの手間が増えることが懸念されています。不適切かつ過度な食品表示を減らし、食の安全を担保することができる一方で、無添加表示が煩雑化していく可能性も否定できません。
2024年(令和6)年3月末までの移行期間が設けられており、ガイドラインに沿った分かりやすい食品表示への移行が求められています。
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。