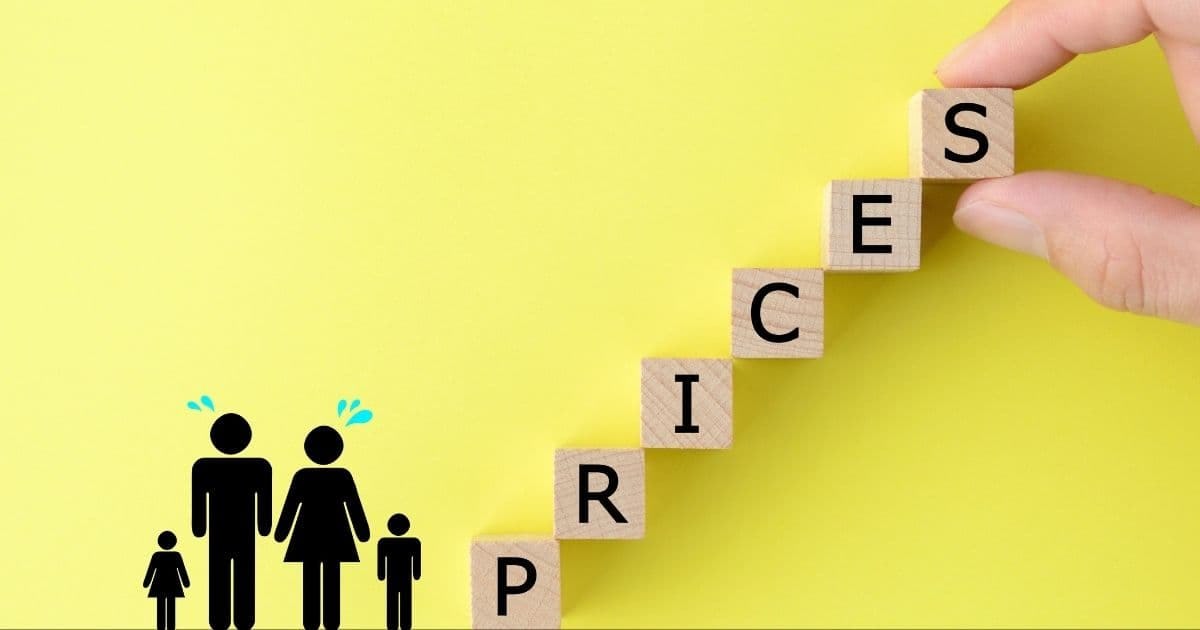
食品や原材料の相次ぐ値上げ、その理由とは?
2021年秋ごろから、大手食品メーカーによる商品価格の値上げが相次ぎ発表されています。食品や食品原材料の値上げが続いていますが、これにはどのような理由があるのでしょうか。そして、なぜこれほどまでに話題になっているのでしょうか。

原油高や円安によるコスト増
<br>食品や食品原材料の価格は、年々上昇し続けています。これは、世界規模での人口の増加や人件費の高騰、地球温暖化や天候不順による収穫量の減少などが主な理由とされています。これに加えて、最近の値上げは脱炭素化の動きやロシアのウクライナ侵攻により原油価格が跳ね上がったことや、急速に円安が進んだことも大きく関係しています。原油高が進むと物流コストが上昇し、円安が進むと輸入コストが増大するためです。
ほかにも、値上げの背景には、コロナ禍での生産規模の縮小や中国の食糧需要拡大などさまざまな要因が絡んでいます。原材料によって値上げの理由は少しずつ異なりますが、食品の原材料の多くを輸入に頼っている日本では、深刻な問題となっています。
特に、小麦粉や植物油脂、大豆、砂糖の値上げが目立っていて、小麦粉を主原料とするパンや、食用油を使ったマヨネーズの価格改定が相次いでいます。これらの原材料の値上げは、冷凍食品や醤油、食肉や魚の加工品、豆乳の価格にも影響します。食品メーカーでは、調達コストの削減や商品のリニューアル、仕入れ量の管理による食品ロス削減などの対策を講じているものの、値上げが止まらないというのが現状です。
値上げが話題になっているのは、なぜか?
値上げや物価上昇自体は、必ずしも悪いものではありません。物価上昇は景気拡大と同調しているケースも多く、商品の値上げにより企業の売上高が増加すれば、社員の給料アップと消費活動の活発化につながるからです。これにより、景気が好調になる可能性もあります。
しかし問題なのは、物価が上昇しているにもかかわらず給料が増えない状況です。不況であるのに物価上昇が進むことを「スタグフレーション」と呼び、昨今の値上げラッシュはこちらに傾いていると言えそうです。1970年代のオイルショック後の日本の状態と似ていて、暮らしやビジネスに大きなダメージを与えます。これは、値上げが話題になっている理由に大きく関わっています。
日本の食品業界だけでなく、食品の値上げは世界規模で進行しています。

 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。




