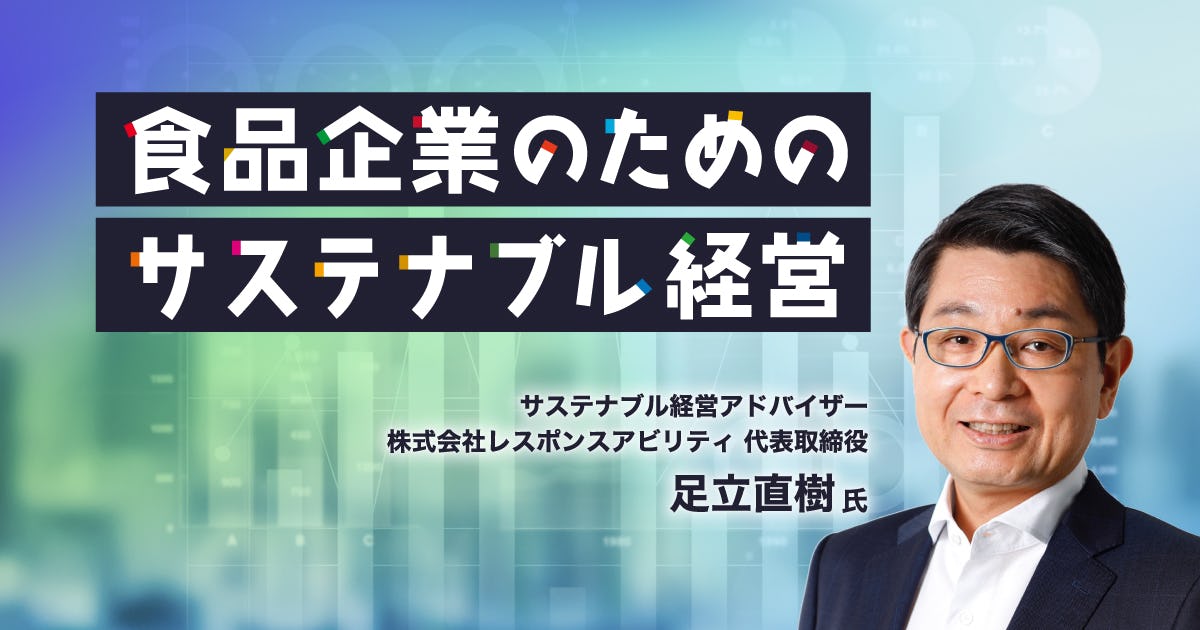
食品企業がサステナビリティを考えなくてはいけないわけ【食品企業のためのサステナブル経営(第1回)】
はじめまして、サステナブル経営アドバイザーの足立直樹(株式会社レスポンスアビリティ代表)と申します。このたびシェアシマinfoで、「食品企業のためのサステナブル経営」というタイトルで連載をすることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。今回が初回ですので、まず簡単に自己紹介を、そしてなぜこのような連載をするのかをお話ししたいと思います。
生態学研究者から環境経営コンサルタントへ
 足立直樹
足立直樹
サステナブル経営アドバイザー。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役。東京大学理学部卒業、同大学院修了、博士(理学)。植物生態学の研究者としてマレーシアの熱帯林で研究をし、帰国後、国立環境研究所を辞して独立。その後は、企業と生物多様性およびサステナブル調達の日本の第一人者として、日本の食品会社、飲料会社、流通会社、総合商社等の調達を持続可能にするプロジェクトに数多く参画されています。2018年に拠点を東京から京都に移し、地域企業の価値創造や海外発信の支援にも力を入れていて、環境省を筆頭に、農水省、消費者庁等の委員を数多く歴任されています。





