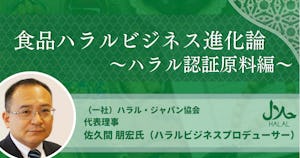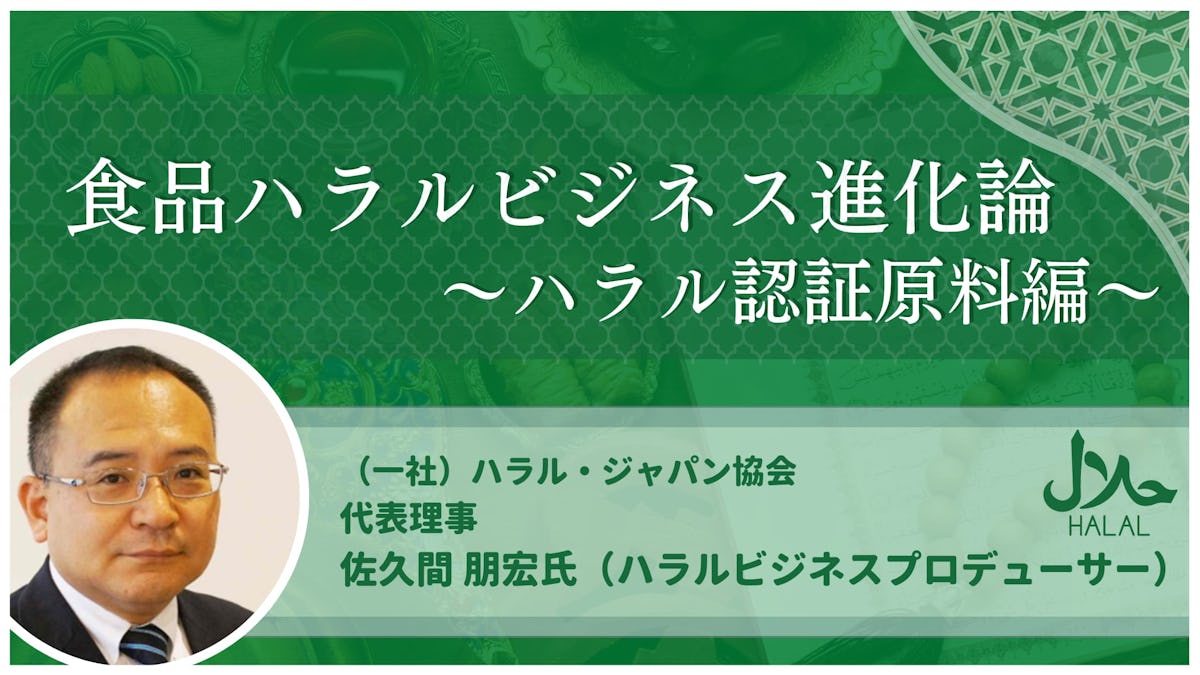
ハラル認証の対象商品とは【食品ハラルビジネス進化論~ハラル認証原料編vol.6】
前回の記事を読む:ハラル認証が有効な国、そうでない国【食品ハラルビジネス進化論~ハラル認証原料編vol.5】
こんにちは、ハラル・ジャパン協会の佐久間です。9月は台風シーズンです。日本列島に毎年いくつかの台風が上陸して大きな影響が出ます。日本は梅雨前線が停滞したり台風の通り道だったりしますが、おいしい水や農作物など恵みもあります、そんな島国ニッポンの原料を世界に発信していきたいですね?今回は第6回となり、全体の折り返しになりますが、よろしくお願いします。シルバーウィーク中の皆さんも多いと思いますが、夏の疲れをしっかり取って、リフレッシュしてください。そして食欲の秋ですから、全国のおいしいものも食べてください!!
今回は「ハラル(ハラール)認証の対象商品は?」を解説していきます。イスラム諸国でも国によって対象商品が違うことをまずは理解してください。
時代と共に変わるハラル認証の対象商品
 シェアシマ編集部
シェアシマ編集部
食品業界に携わる方々に向けて、日々の業務に役立つ情報を発信しています。食品業界の今と未来を示唆する連載や、経営者へのインタビュー、展示会の取材、製品・外食トレンドなど話題のトピックが満載!さらに、食品開発のスキルアップや人材育成に寄与するコンテンツも定期的にお届けしています。