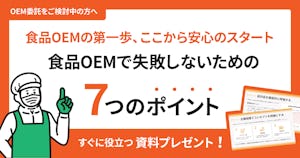【富士商事】チャット形式でサクサクやり取り!サンプル取り寄せが簡単・スピーディに
ゲル化剤「パールアガー」シリーズを展開する、ゲル化剤メーカーの「株式会社 富士商事」(東京都中央区)。主力の「パールアガー8(エイト)」は常温で溶けない特徴を持つゲル化剤の先駆けであり、同社の代名詞とも言える存在です。自社の商品の強みを生かした食品開発のため、サンプル原料の調達の際にシェアシマを活用しています。
以前であれば、形式ばったメールのやり取りから始め、実際にサンプルを入手するまでには、何往復もやり取りを重ねていましたが、「そのようなわずらわしい手続きから解放された」と言います。担当の町田健さん(研究室主任)が『LINE世代』ということもあって、チャット形式でやり取りできるメッセージ機能が気軽で重宝しているとのこと。実際に商品開発に採用になった場合には、取引先に原料メーカーを紹介できるため、「関わる事業者がウィンウィン(Win-Win)な関係を築くことができる」とおっしゃっていました。
担当者に直通で負担が軽減
同社の主力商品「パールアガー8」は、海藻から抽出・精製された多糖類を原料としたゲル化剤です。無色透明のため「素材を生かした商品作りができる」点が特徴で、ゼリーやプリンなどに使われています。商品の魅力を引き出せる新たな活用法を探るため、町田さんが属する研究室では日頃から試作品づくりを行っています。中には手に入りづらい食品原料もあり、イメージを具現化するのに苦労することも多いそう。そうした中、シェアシマを利用するようになってからは、「サンプルを取り寄せるハードルが下がった」ということです。
ウェブサイトを眺めるだけで食品原材料を探せる手軽さはもちろんのこと、売り手ユーザー側はサンプル取り寄せがあることを前提で商品を掲載しているので、とんとん拍子で話が進むのだそう。通常なら電話で問い合わせた上で、「お世話になっております」というお決まりのあいさつをメールで交わすことから始まるのを、シェアシマなら直通で担当者にメッセージが届けられます。しかも、そのやり取りが文字として残るので、「情報の行き違いが防げることも大切なポイント」だと言います。
日頃の情報収集はシェアシマで
同社の川端史典さん(研究室次長)は、農水省や厚労省が配信するメールマガジンと併せ、シェアシマinfoの食品安全・衛生・行政情報(毎週月曜更新)もチェックしています。「デスクで見る時が多く、日頃の情報収集に役立っている」と言います。
シェアシマユーザー向けにオンラインで配信している「シェアシマ商品開発オンラインセミナー」も、関心の高いテーマの際には研究室に呼び掛けて、メンバーと共に視聴しています。とりわけ、コロナ禍では東京から地方へ出向くことができず、一番の情報源であった展示会も軒並み中止となったため、「貴重な情報源として重宝した」ということでした。少しずつ感染者数も落ち着いてきましたが、今度は海外から仕入れる原料の値上げに悲鳴を上げている状況です。
作った人と食べた人を、笑顔でつなぐ─。すなわち「笑顔のもとをつくる仕事」をしているという同社。厳しい中でも工夫と努力を積み重ねて、日々研究・開発に励んでいます。